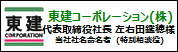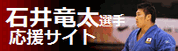2017年8月のページ
2017年
8月
29日
火
大学助教と中学生の風変りな付き合い方

当時、中学生だった私と、同志社大学哲学科で助教をされていた北出寧啓(やすひろ)という先生との付き合い方が、今思えば風変りだったので、今回は、そのことについて書いてみたい。
まずその前に、父子共にお世話になり、母の命の恩人でもある金田半三郎先生という方を紹介したい。
金田先生は、京都大学医学部の元準教授(のちに金田医院を開業)をされていた医学博士(当時 血液腫瘍学)で、父がサラリーマン時代に在籍していた会社の産業健診医であったことから、父と親しくしてくださった。
また私の幼少期の主治医でもある。そして私の中・高校生時代の柔道私設後援会会長もしてくださった。
また亡き母の腎臓に潜伏していた結核菌の存在を最初に発見してくれた先生でもある。先生の発見が無かったら、単なる風邪引きからの腎盂炎と考えてしまい、結核菌に対する治療が遅れて、母の人生はさらに短いものになっていただろう。
金田先生は数年前にお亡くなりになられたが、認知も無く90歳という天寿を全うされた。
(合掌)
その金田先生のご紹介で、私が中学生の時に、クラブ活動(柔道・少林寺拳法)に専念し過ぎるあまりに遅れてしまった勉強を取り戻すべく、中学3年間に渡り、週1回のペースで自宅に来て英語・数学を教えてくれていた先生がいた。
その先生が冒頭で紹介した当時27歳、同志社大学哲学科で助教をされていた北出寧啓(やすひろ)という先生で、のちに市民運動家として泉南市議会議員を3期に渡り勤められた方である。
前置きが長くなってしまったが、学問を教わる以外にも、北出先生が金田先生の付き人のような感じで、当時の私の自宅によくみえられていた。
父と金田先生が話している間、必然的に北出先生と私が共有する時間も増えて行った。
そんなある日、北出先生は中学生の私に向かって、こう言い放ったのである。
「私は、人とたわい無い話で時間を潰すような刹那的な時間の使い方はしたくない。付き合うからには、君と僕とでもっと文化的・建設的な議論をしよう!」
そう言うと、鞄から、ヘミングウェイの「老人と海」を取り出し、
「次回、会うまでにこの本を読んでおきなさい。そしてこの本についての感想を議論し合おう」と一方的に言われたのである。
私は先生の身勝手な言い分に、心の内では憤慨していた。
しかし本を読まずに済ますことは、勝負から逃げたような、そして北出先生に負けたような気がしたので、しぶしぶ本を読んでみることにした。
私は歴史が好きだったので、歴史関係の本はよく読んではいたが、文学作品はまるで興味が無いどころか、「男が読むもんじゃない」とバカにして毛嫌いしていたのである。
しかし読み始めると面白くて堪らない!老人とカジキとの闘い、また老人と若者の遣り取りが痛快でハマりにハマりまくった!あまりの面白さに何度も繰り返し読み返した。
それから暫くして北出先生と議論し合う機会が訪れた。
私が「待ってました!」とばかりに一連の感想を得意顔で語り終えると、
「確かに物語に書かれた表面上の事柄は理解し読み込めている。しかしそれではダメだ!行間に書かれている作者が言いたかった事が読み取れていない!」と叱咤された。
「そんな事はこの本のどのページにも書かれていない」と私が怒ると、
「当たり前だ!そんなことは作品のどこにも書かれていないが、それを読み取れるようになることが文学を嗜むということだ。その為には、たくさんの文学作品を読み込んで行くしかない!」と仰られて、その後、次々に本を渡されるようになった。
「走れメロス」「破壊」「人間失格」「吾輩は猫である」「城崎にて」「雪国」「羅生門」etc・・・・、中学卒業まで北出先生との文学作品を通した暗闘は続いた。
正直、当時は北出先生を敵だと思っていたが、いま考えると私の偏った読書の改善と教養を広げるためにお付き合い頂いていたのだと思う。
北出先生との出会いがなければ、数々の有名な作品を食わず嫌いし、軽んじたまま過ごしてしまうところであった。
2017年
8月
20日
日
忘れることを前提にする

・営業に必要な資料を会社に忘れた
・頼まれていた仕事をウッカリ忘れた
・レンタカーを借りたのにETCカードを持って来るのを忘れた
・ガソリンを入れ忘れ、残りが少ない
上記のような失敗の経験は、多かれ少なかれ、誰でも経験があるのではないだろうか?
朝、外出の用意をしている最中、頭の中ではアレやコレや違うことを同時にいくつも考えていて、そのままパーッと出掛けてしまうので、以前の私は忘れ物が多かった。
そこで、少しでも忘れる事(物)を減らすために日頃から心掛けるようになったことがある。
それは「忘れることを前提にする」のである。
「明日の営業、俺はきっと出かける寸前にバタバタして、この資料を持って行くのを忘れるだろう」と考えるのである。
じゃぁどうするか?答えは簡単で、明日乗って行く車に、今すぐ資料を積んでおくのである。
他のシーンでも、忘れてはいけない持ち物があれば、玄関のドアの前に前夜から置いておく。
レンタカーの際のETC問題も、カードを2枚持ち、内1枚は常に財布に入れておくことで解決した。
ガソリンの入れ忘れは、面倒くさがらず4分の3を切る前に小まめに入れるように心掛けている。
出張先などでコインロッカーに荷物を預けた時は、そのまま忘れて帰らないように、ロッカーのカギを財布の中に入れる。カバンの中に入れると、そのまま奥底で気づかないこともあるが、財布だと帰宅するまでに何度も開くので、絶対に気づく。
数か月先のチケットなども、封筒に入れたままにしておくと、何かの拍子に間違って捨ててしまう可能性があるので「捨てるな!チケット在中」と自分に向けて、その封筒にメモを貼り付けておく。そして予定が近くなって来たら、気づいた時に、もう財布に入れておく。
このように、忘れることを前提とするようになってから、忘れ物は減ったと思う。
「頼まれていた仕事をウッカリ忘れた」を防止するためにしていることは、今すぐすることである。小さな、すぐに済む用事こそ忘れやすい。
「この仕事が片付いてから取り掛かろう」と思っていると、ついウッカリ忘れてしまう。
だから、すぐ済む用事なら後回しにせず、すぐ済ませるようにしている。
私は、しなければならない事を後回しにして、なかなか着手しないでいるのが我慢ならない。自分でもスグやるが、社員やスタッフ達にも、彼らが後回しにしていることに着手するまで、ずっと「すぐ!すぐ!すぐ!今!今!今!」を言い続けるので、きっと閉口している人もいることだろう。
口うるさくて申し訳ない。
と謝りながらも、今後も口うるさいのは変わらないであろう。
(関連記事:すぐ!すぐ!すぐ!今!今!今!>>)
2017年
8月
07日
月
地獄掃除のその上

以前、地獄掃除>>という題名で、私の掃除に対するこだわりを綴ったが、その地獄掃除を標榜する私が、「もう許してください!」と思わず言ってしまうほど凄まじい掃除を行われる、M社長という方が奈良県にいらっしゃる。
同じ高校の出身ということもあって、私が若い頃からお仕事をくださっている中小企業の社長で、公私とも大変お世話になっている大先輩である。
こんな事があった。
車にて所用で大阪より名古屋に行った帰り道、翌日の商談に必要な商品サンプルを届ける為にM社長の本社に午後7時ごろお伺いした。
すると、本社の窓という窓が玄関扉も含めて1枚も入っていないのである。
理由は全ての窓を午前中から外して、本社横の駐車場で水洗いし、乾かす為に外しているとのことだった。
私も掃除には、かなりの「こだわり」があり、今後の掃除方法の参考にしたいので早速、手伝わせていただくことにした。
さて見渡すと、窓だけでなく同時に、強固なボルトで留まった外側の面格子や網戸も外して、それらまで洗浄して乾かしてる。その上、窓枠の隅々まで爪楊枝でほじくり返えすように掃除してある。おまけにそれらを元に戻す際、すべてに汚れ止めのコーティング処理をして、仕上げ拭きを光り輝くまでするという。
そしてこれらを月毎に年12回繰り返しているらしい。
聞くとその時の終業時間は毎回、午前0時くらいになるらしい。
そして手伝わせていただいたその日も、全ての作業が終わったのは、午前0時を超えてからだった。
他にもM社長自らが先頭に立って、
毎月、便座を外しての大掃除、本社内の水回り配管、外側の排水溝の大掃除、廊下の端や壁紙の隙間まで「爪楊枝で掃除」、すべての家具の引き出しの中身の大掃除。
また年3回、定期的に、社内の物をすべて撤去しての床掃除とワックス掛けから始まり、内壁&外壁を磨き上げ、屋上までワックスを掛けて掃除するという。
これが毎日始業前1時間の掃除をしている上に行われるのである。
そう言えば、M社長の本社は建築後25年くらい経つが、新築時とほぼ変わらない状態を今も保っている。
さらにまさかのエピソードだが、ゴルフに行った時に、そこのロッカールームとトイレの掃除が気に入らず、その日はゴルフをせずに1日中、それらを掃除して帰ってきたことがあるらしい。
まだまだM社長の掃除ネタは枚挙にいとまがないが、これくらいで、その「凄まじさ!」を想像してもらえると思う。
M社長の会社と当社の掃除を比べると、「やり方」や「こだわり」については、さほど違いが無いが、「掃除の回数」と「かける時間」が違う。
M社長の会社は毎月大掃除があるが、当社は毎朝30分の掃除の他には、大掃除は年に3度と私が「掃除が行き届いていない!」と感じた時ぐらいである。
しかしM社長と同じことを出来ないとは感じない。
「うちの会社では、そんなことムリだな」と諦めてしまうのではなく、工夫して少ない大掃除の回数でも綺麗に保てるようにしたり、短時間で効率よく掃除が出来る方法を考えたりなど、「形を変えた最善」でM社長の会社の清潔さに迫ることは出来ると思うのだ。
何事もそうである。
出来ない・・・と最初から決めつけて諦めてしまう前に、少しでも目標に近づけるように工夫することが大事である。