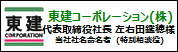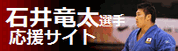2017年5月のページ
2017年
5月
28日
日
興味を持たせる話術

高校1年生の時に古典の授業で、紫式部の源氏物語に触れる機会があった。
しかしながら、バンカラ学生であった私は、そんな雅な世界の物語には興味が持てず、スグに耳に蓋をしてしまった。
授業で頭に入ったのは「紫式部は源氏物語を書いた人」という1行の情報だけで、源氏物語の内容も、何を教わったのかも、記憶にない。
そしてそこから2年が経過して、今度は高校3年生になって「地学の授業」で再び源氏物語に触れることになった。
この授業を持たれていたのは、四国の理系の大学を出られたTという男性の先生であった。
私の目からは「ザ・研究者」という言葉がピッタリの少し神経質そうに見える先生だったと記憶している。
当時、低気圧や高気圧・偏西風・気圧配置などの単語の説明に始まり天気図の見方を先生は解説されていたが、私は椅子の背もたれに背中をあずけながら、ぼんやりと聞き流していたように思う。
その授業の半ば、
「君たちが1年生で習った源氏物語を読むと、紫式部は気象学者だったことが見えて来る。」と先生がおっしゃられた。
(紫式部が気象学者???なんでや?)
思いがけない言葉に疑問を持ち、そして興味を惹かれた私は、思わず身を乗り出した。
「ザ・研究者」風の理系の先生から紫式部の話が出るアンバランスさも面白くて、皆が先生の話に意識を引かれたようだった。
そのタイミングで、T先生は事前に用意していたプリントを皆に配布してくださった。
そこには、源氏物語の気象について書かれてある部分を幾つか抜き取って箇条書きにしてあった。
当時の事なので完璧には思い出せないが、「春霞、春雨、夕立、秋しぐれ、野分、・・・・」など様々な気象と、気象について書かれた文章を太字にしたものが挙げられていた。
そしてT先生は、「源氏物語に書かれている気象に関する文章は、とても正確で、時系列で読み解けば、その期間の天気図さえ推測することが出来る。
たとえば台風が出てくる章があるが、書かれている文章から台風の特徴や進路まで分かる。」
というような事をおっしゃっていた。
私は知らず知らずのうちに、熱心に耳を傾けていた。
「紫式部」にも「天気図」にも私は興味が持てず聞き流していたが、「紫式部は気象学者」という意外性のあるキャッチフレーズ(掴み)に疑問を持ち、そして意識が引き付けられた。
人と異なる着眼点から話を展開させて行った この時の地学の授業への驚きは、少なからず私に影響を与えた。
経営者になった今でも、社員教育を実施するときに、よくこの手法を使っている。
先日も、車で九州に2日間出張する社員に「安全運転を心がけて下さい」では右から左で意識に留まらないだろうと思い、「虹と安全運転とは同じである」という話をして送り出した。
紙面の都合もあるので内容については皆様の推測にお任せしたい。
2017年
5月
21日
日
全部ダメでヘタだった!

「社長!申し訳ございません。皆は頑張ってくれたのに私は全然ダメで運営もヘタでした!」
これは、私に向かって頭を下げるS部長の言葉である。
話は遡る。
今月の頭、第3回フラワーホームカップ>>を開催させて頂いた。
フラワーホームカップは当社の「社会福祉の向上」と「地域社会への貢献」への取り組みの一環として、昨年度より開催させて頂いているグラウンドゴルフの大会で、毎回約200名の高齢者の方々が参加してくださっている。
本社の役員改選に伴い、フラワーホームカップの責任者を今回から変更することになり、丸竹NO,1のゴルフの腕前を見込んで、本社のS部長を責任者に指名した。
S部長は泉南市体育協会や泉南市グラウンドゴルフ協会の方々との打ち合わせや日程調整に始まり、大会までの約2か月の期間、日頃の業務の合間を縫うようにして東奔西走してくれた。
大会の前日、仕事が終わった後、もう外は真っ暗であったが、私はフト思い立って大会会場である、なみはやグラウンドに行ってみることにした。
横断幕を張る場所やテントのことなど諸々、もし本番で手間取ったら、段取り良く指示が出来るように下見をしておいた方が良いと思ったからである。
しかしグランウンド横の駐車場に車を近づけると、S部長の自家用車が止まっていた。
私はそのまま車を方向転換し、その場を後にした。
各協会の役員様やS部長を中心とし、またスタッフ一同の尽力により、事故もなく天候にも恵まれて、今大会も皆様に喜んでいただけた大会になったと思う。
翌日には一般参加者の方が、わざわざ本社の電話番号を調べてお礼の電話を下さった。
その後、S部長の労をねぎらおうと、私の机に呼んだわけであるが、彼は私の目の前に来るなり、
「社長!申し訳ございません。皆は頑張ってくれたのに私は全然ダメで運営もヘタでした!たぶん社長の思い描いていたような形にはなっていないし完璧ではなかったと思います。ほんとすみません。次回はもっと緻密に組み立てます。」というのである。
表情をみるとS部長が謙遜して言っているのではないことが即座に読み取れた。本当に心底落ち込んでいたのである。
私が大会全般を通して気付いた点を具体的に並べて、どれだけ「良かった」と評価しても、S部長の顔は曇ったままだった。
私が「そしたら、どこがダメだったのか?どこがヘタだったのか?」と聞いても、具体的に話せば責任転換や言い訳になってしまうと思ったのかもしれない、
彼は、しばらく押し黙った後「全部です!」と答えるだけであった。
私には分からなかったが、彼が思い描いた理想の形と比べて、満足いく結果じゃなかったのだろう。
実は私は「全部ダメでヘタだった!」と落ち込むS部長を見て、嬉しい気持ちになった。
もし彼が「妥協する人」であったなら落ち込むことも無かっただろう。「もっと良く出来たはずなのに」と思うからこそ、向上心があるからこそ、悔しくて落ち込むのだろう。
失敗して落ち込んでそのまま自信を失ってしまう人も居るが、彼はそうじゃない。落ち込む度に自分の中のマイナスな感情と戦い、省みて、考え、成長して行く人物である。
用意はしていたのだが今回は、あえてS部長にありがとうカード>>を手渡さなかった。
理由は、彼自身が満足していないのに、ありがとうカードを手渡すと失礼になるのでは?と思った。そして同時に、彼の今後の伸びしろに期待を掛けたからにほかならない!
2017年
5月
12日
金
障害者について 3

当社が製造事業部門で、障害者の雇用を始めるようになって数年経った頃、たしか平成7年頃の話である。
大阪府立砂川厚生福祉センターの先生の紹介で、大阪府立佐野養護学校(当時)から、I君という20歳の男子卒業生を真空パック工場で雇って欲しいとのご依頼があった。
I君は身体的には何の障害も無いのだが極度の自閉症であり、お母さんとは何らかのコミュニケーションが有るらしいが、母親以外の人とは一言も話さないし、担任の先生とも入学以来、言葉はおろか目も合わせたことが無いという事であった。
その後、I君は担任の先生に付き添われて面接のために来社してきた訳だが、事前に聞いていた通り一言も話さないばかりか、確かに目も合わさない青年であった。
自閉症の方の雇用は初めてだったので不安はあったが、ハンディキャップがある人に対しても雇用の機会を創出していく事が、経営者の「義」であり社会的責任と考えていたので、その場で採用を決めた。
当時の真空パック工場の責任者であったM工場長と対応を協議した結果、「最初は特別なことはせず、すべてに渡りごく普通に接しよう」「その後、状況を見ながら判断して行こう」という事で意見が一致して、いよいよ出勤初日を迎えたのであった。
桜の季節、I君はお母さんと共に出社してきた。
「息子が慣れるまで暫くの期間、私も8時間、工場に居ても良いでしょうか?」という事前の申し出があった為、他の社員達にも事情を話し、皆が快諾していた。
椅子を勧めてもお母さんはI君のすぐ傍に立ち、息子の作業に間違いがないか、終業までの8時間、見守り続けた。
このような事は初めてだったので私は少し困惑した。
翌日も、その翌日も、お母さんは椅子を断り、I君の作業を傍で見守った。
途中から気づいたのだが、トイレもI君の休憩時間に合わせて行くほどであった。それほど片時も息子から目を離さなかった。
お母さんのやり方が正しいのか間違っているのか、そんなことは私には分からない。
しかし、悲壮なまでの責任感と全身全霊をかけた愛情を、私は見たおもいだった。
お母さんは5月になっても毎日工場に来てI君を見守り続けた。
この頃には、工場の隅の椅子から彼を見守っていた。
日によっては午前中に家事や用事を済ませてから来る日もあったが、毎日朝から夕方まで工場で過ごすのは大変なご苦労だったと思う。
I君のコミュニケーション能力については1か月経っても何ら代わり映えしなかったが、業務内容については単純作業という事もあり何の問題も無く、他の社員と変わりなく働いた。
お母さんは6月になっても毎日工場に来ては片隅に座っていた。
ある日、私はお母さんに「もう見守る必要がないのでは?」と言うと、
「すみません。家に居ても心配で心配で何も手につかないんです。ここで息子を見守ってる方が、気持ちが楽なんです。」と返ってきた。
梅雨が終わって、夏が本格的に始まっても、お母さんは毎日工場に来た。片隅の椅子に座って本を読んだりしながら、合間合間に顔を上げて、I君を見守っていた。
私はその姿を見る度に、母の子に対する慈愛の深さに驚くと同時に、亡き母を思い出して郷愁を覚えた。
その年の秋になって繁忙期に差し掛かると、真空パック工場は猫の手も借りたいほど忙しくなった。I君のお母さんは相変わらず工場に通って来ていた。
そこで私は「人出が足りなくて困っています。お母さん、出来れば当社で短期アルバイトとして働いてもらえませんか?」と声を掛けさせてもらった。
人手に困って出た言葉であったが、お母さんは「ほんとにいいんですか!?」と快諾してくれ、その日から一緒に働いてくれた。
この後、数日してI君にある変化が訪れた。
それまでは一日中、たとえお母さんとでも、社内ではほとんど無いに等しかったコミュニケーションが、仕事中にお母さんとは何らかのコミュニケーションを若干しているのである。
私にはそれがI君の小さな進歩に思えた。
秋も終わり、冬が始まり、正月も過ぎ、春の気配を感じる頃、I君はまた少し変わった。
「おはよう」と声を掛けると、今まで完全に固まっていたI君であったが、目は合わせないが小さく頷くようになったのである。
春になり真空パック工場の繁忙期は終わったが、もうそのままお母さんはパートとしてI君と一緒に働いてもらうことにした。
I君は、畳の目を数えるような変化ではあったが、少しずつ少しずつ変わって行った。
それまでずっと無表情だったのが、声をかけると口角を少し上げるようになった。また一瞬ながらも、こちらの顔を見ながら頷くようになった。
2年半が経つ頃には、毎朝「おはよう」と声を掛けると、何らかの唇の動きを見せて、一瞬こちらに視線を向けて若干の笑顔を見せてくれるようになった。
3年が過ぎた頃、I君のお父さんが転勤することになり、I君もお母さんも退職することとなった。
退職する最後の日に、私が一か八か握手を求めると、I君は手を差し出してきた。
たかが握手かもしれないが、最初の頃のコミュニケーションを思えば考えられないことであった。
私が手を握ると、I君はまたうつむいてしまったが、間違いなく握り返してきた。
そのI君の姿を見てお母さんは泣いていた。私も感動して涙が出た。
I君の成長が嬉しかった。最初の頃、きっと不安な気持ちで工場の片隅の椅子に座り続けたお母さんが今喜んでいる姿が嬉しかった。
この時の経験が、今も継続して障害者雇用に積極的に取り組んでいることに繋がっている。
当時、「障害者本人の個性に、周りが寄り添う気持ちさえあれば、その個性は良い方に変化して行く」という事に確信を持つに至った次第である。
●第3回フラワーホームカップを開催いたしました。