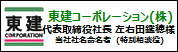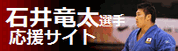2013年
3月
28日
木
川柳は頭のトレーニング

私の趣味の一つに、川柳作りがある。
いま世間では川柳ブームだそうで、川柳本が大ヒットしていると先日テレビが紹介していた。
例えばシニア世代の川柳を集めたシルバー川柳本。
「目覚ましの ベルはまだかと 起きて待つ」
他には、薄毛をネタにした毛髪川柳本なども売れているそうだ。
「落ちていた 俺の名刺の 裏に「ハゲ」」
私は、どちらかと言うと自分で川柳を作るのが好きだ。満足いく句が出来た時の達成感にはまった。
題材は、慣れ親しんだ柔道に関する川柳を作ることが多い。
ここで一句。
「勝ち方も 礼儀作法の ひとつかな」
この句は第一回ホームメイト川柳の柔道部門に投稿させて頂いた句である。
国際試合などを見ていていると、中にはマナーの悪い勝ちをする選手も居て、腹立たしく思う時がある。その鬱憤を皮肉に変えて詠んだ。
・・・と、そんな事を言ってる私だが、高校生の時には「どんな勝ち方でもイイから勝ってやる!」と思って、碌でもない勝ち方をした事もある。それも一度や二度じゃない。
そんな自分への反省も込めているので、私の高校時代を知ってる人は「お前が礼儀を言うか!!」とは言わないで欲しい 笑
川柳は、たった17文字の文章である。
その17文字に思いの丈をぶつけ、しかも読み手にイメージを伝えないといけないのだから、川柳を考えている時は頭の中はフル回転である。
詠みたい事柄のイメージを頭の中で膨らませ、その事柄をどのように捉えるかを考え、次々に思い浮かぶ言葉を取捨選択する。
まさにイメージ創出トレーニングであり、脳の活性化トレーニングである。
これは当社比ならぬ私比であるが、川柳の投稿を趣味とするようになってから、頭の回転がスピードアップしたように思う。
私の趣味が川柳作りだと聞いて、爺臭いと思った人もぜひ力作の一句を詠んでみてほしい。
きっと脳が生き生きとして来るのを感じられるだろう。
2013年
3月
19日
火
不条理を学べ

スポーツとは誠に不条理なものである。
血の滲むような努力をしても、その努力が結果に反映されるとは限らない。
スポーツの中でも特に相手と直接対戦し勝敗を決める対人競技は、不条理の極みと言ってもいいぐらいだ。
私が学生時代に取り組んでいた柔道などもその典型的な例だ。
努力の積み重ねで、確かにある一定のところまでは登って行ける。
けれども血の滲むような努力を重ねた者同士の戦いでは「運」が勝敗を分けたりする。
運は自分でコントロール出来るものではないのに、運が結果を決めるだなんて、誠に不条理な話である。
けれどもそれでいいのだ。
学生時代に熱心にスポーツに取り組む者は数多く居ても、プロのスポーツ選手になる者はほんの一握りである。
学生スポーツで重要なのは、努力が実る喜びを知る事はもちろんとして、自分の限界まで努力をし「心」「身」ともに厳しく鍛えることにある。
そしてその最大限の努力が結果に反映されない不条理さを学ぶことも重要な事じゃないだろうか。
一歩社会に出れば不条理なことだらけである。
現代の社会は激烈な競争社会。グローバル化も相まって社会はまさに戦国、弱肉強食の時代である。
そんな中でも私が何とか中小企業の態を為し、どうにか今日までやってこれたのは、学生時代に柔道の厳しい修錬を経験したことや、社会で通用する不条理を学べたことが大きな一因になっていることは自分自身にとって疑う余地がない。
つまり柔道により競争社会を生き抜く「心」が作られたのだ。
偉そうな事を書いている私だが、もちろん学生時代は勝つことのみが目標で、それ以外の意義を見出すことは頭に無かった。
優勝して自己目標を達成するという第一の意義以外にも、社会を生き抜く心を作るという第二の意義がスポーツにはあるという事を、社会に出てからようやく色々な場面で自然に、また必要に迫られて気付くことになった。
この記事を書きながらこんな言葉を思い出した。
「精力善用」(精力最善活用)
「自他共栄」(自他融和共栄)
講道館柔道の創始者・嘉納治五郎師範の言葉である。
2013年
3月
12日
火
困った時はお互い様

未曾有の災害であった東日本大震災から約2年の月日が経ちました。
お亡くなりになられた方々に深く哀悼の意を捧げると共に、被災地の皆様におかれましては、まだまだ大変な状況に変わりはないと思いますが、一日も早い復興をお祈り申し上げます。微力ではありますが、今後も継続して復興支援させて頂く所存です。
さて、私は震災関連の仕事をさせて頂いている関係もあり、ボランティアや支援活動などに参加させて頂くことが度々ある。
東日本大震災では、外国人ボランティア達との会話で印象的なことがあった。
3月11日の震災後、世界各国からボランティアの方々が日本に訪れてくれたが、その当時は関東より北の空港が使えなかった。その為に多くの外国人ボランティアが関西国際空港経由で東北入りをした。
私は、その方々の送迎と陸路乗り継ぎのお手伝いを異業種交流会の皆さんとさせて頂くことになった。
航空会社の方から引き継いだ後、切符を手配しJRのボランティアの方と同行し駅まで案内するというものだった。
私は日本語以外ろくに話せないので普段の饒舌は鳴りを潜めていたし、外国人ボランティア達も移動の疲れや緊張があったのか互いに口数少なく、ただ漠然とお弁当やサンドイッチとお茶・コーヒーをお渡しして、簡単な挨拶をかわして見送るだけの繰り返しであった。
しかし帰路の際は違った。
飛行機の出発時刻の関係で、時間に余裕があったのも要因だが、一様に同じ質問をほとんどの外国の方から受けた。
「なぜ日本はこのような事態でも略奪や暴動、窃盗、治安悪化が起こらないのか?」
「世界各地にボランティアに行ったが、こんな事はこの国だけだ。」と。
私は、どう答えて良いのか悩んだが、とっさに
「日本の精神文化とアイデンティテーの中に、仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌という概念があり、そのうえ農耕民族であるが故に共同体意識が高く、昔から相互扶助という文化が有り、それから起因する道徳性の高さからです。」と答えた。
先にも書いたように私は英語は出来ないので、通訳の方を通しての会話である。
その通訳のかたは専門の方ではないのだが、何とか私の言葉を伝えてあげようとかなりの時間と全精力を費やしして、身振り手振りを含めて挑んでくれた。
しかし完全には伝わらなかった。
通訳の方の「何か簡単な言葉で説明できる日本語は無いですかねぇ?」という問いかけに私も必死で考えた。
そこで苦し紛れに思いついたのが「困った時はお互い様文化」という言葉だった。
通訳の方はまたもや必死で全精力を注ぎ、忘れている単語も思い出さんばかりに奮闘してくれた。
外国人たちが、うんうんと頷きながら耳を傾けている。
どうやら通訳の方の頑張りの甲斐があって 、通じたようだ。
胸を撫で下ろしていると、話を聞き終えた外国人の方が満面の笑顔で私に握手を求めてきた。
そうして突如「オ・タ・ガ・イ・サ・マー!」と口にした。
私も丁寧に頭を下げ「サンキュウベリーマッチ」というと、「ア・リ・ガ・ト・ウ」と返事が返ってきた。
そして一同、爆笑に包まれた見送りとなった。
後で聞いた話だが、「日本人のほとんどは聖書を読んだことが無いはずなのに、ちゃんと聖書に書いてあることが出来ている・・・。お互い様の文化は聖書にも通じる素晴らしい文化だ・・・。」みたいなことを、外国人の彼らは言っていたそうだ。
それを聞いて、先年亡くなったインドのある高名な宗教家の言葉を思い出した。
「神は一つ、あなたの信じる神に手を合わしなさい。」
信じる神は違えども、信じて祈る気持ちは皆同じ・・・・と私は勝手に解釈をしている。
またこの時の事は、共通言語を踏まえて人と人が語り合い、互いの理解を深め合うことがいかに大切かを再認識させられた出来事であった。
人は「違い」にばかり目が行きやすいが、「共通する部分」「通じ合える部分」も沢山あるだろう。
そちらの方へ目を向け、互いに理解し合えれば「助け合い」や「お互い様」で、地球上から紛争や戦争、外交・領土問題も無くなり、きっと平和な地球になるのではないだろうか?
理想論だろうか?
しかし、そうなって欲しいと祈るばかりである。
2013年
3月
04日
月
トイレ掃除を侮ることなかれ

私は運気を上げる為にも掃除、その中でも特にトイレ掃除を心がけている。
ある時、そのことを知人に話すと、「風水とか迷信のたぐいですか?そういうのは、あまり信じられないなぁ」と言われたことがあった。
しかし風水や迷信は荒唐無稽なものではなく、きちんと理にかなったものが多い。
例えば風水では家の中心や北東に浴室を設けるのは凶と言われているが、衛生面 から考えると納得できる。北東に浴室を置くと早朝ぐらいしか日光が当たらないため、1日中ジメジメしていてカビや雑菌が繁殖しやすい。家中に菌が蔓延すると家族の健康状態が悪くなる。
こういった具合だ。
私のトイレ掃除にも理由がある。
例えば美味しい料理を出すレストランに行ったとして、そこのトイレが汚れていると、客の目に触れない厨房では、どんな具合に衛生管理されているのか不安になる。
何事も一事が万事だからだ。
トイレを清潔に出来ないレストランが、厨房を清潔に出来るはずがない。
それと同じことが、製造業である我が社にも言えるから、私は掃除に拘っている。
最も汚れるであろう場所のトイレを清潔に保つ、職場を清潔に保つ、そうして毎日掃除をし手を掛けている物には自然と「丁寧に扱おう」という気持ちが沸いて来る、そういう気持ちが芽生えた者は、商品や材料、器械も丁寧に扱うようになる。
我が社から送り出す商品だけを結構にするんではなくて、取引先からは見えない部分もおろそかにしない。
わずか一つの行動が、全てに繋がっているのだ。
人が見ていようが見てまいが、精一杯する。
人が嫌がる仕事ほど進んでやる。
この事は回りまわって、きっと幸運と言う名のチャンスを運んで来るだろう。
トイレの汚れに気づけない者も居れば、気づける者も居る、気づいて知らぬふりをする者も居れば、綺麗にしようとする者も居る。
その差は極めて大きい。
自ら進んでするトイレ掃除には「気付ける力」「実行力」「奉仕の精神」が必要なのだ。
たかがトイレ掃除と侮ることなかれ!