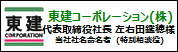私は元気な母を知らない。
元気に振る舞っていても、母は常に病と隣り合わせに居た。
私の、母の記憶は和歌山市にある日本赤十字病院の病床から始まる。
母は私が生後8か月目に重度の腎機能障害に罹り入院を余儀なくされた。
3年後に退院するも腎機能が落ちていたせいか、今度は銭湯で尿路感染による腎臓結核を患い、その後また約1年間、保菌検査が陰性に転じるまで入院した。
父が「あのとき自宅に風呂が有ったなら」と苦しげに呟いたことがある。
その 時の哀れな想いからなのか、父は「貧乏は罪悪だ」としばしば言うようになった。
しかし腎機能とは怖いものである。
1度悪くなるともう完全に回復するということはない。
臓器の中でも心臓や肺に次いで治療の難しい臓器だそうである。
母は年々、機能が低下していき入退院を繰り返しながら、数年後には腎不全に陥り人工透析を始めるに至った。
これがまた週3回、1回6時間も(亡くなる前は毎日)透析をしなければならず、副作用も酷く、苦しそうにしていた母の姿が、やる瀬ない想いと共に浮かんで来る。
母が亡くなった時、母の姉が傍らで「これでもう透析をしなくてよくなったね」と言ったそうだが、その言葉が忘れられない。
私の、母と暮らした記憶は5才前後から始まる。
それまでは母方の祖父母の家で育てて貰った。
幼少ながらその頃すでに、母がいつ死ぬかもしれないという恐怖が常に身近にあり、「死んだらあかん!!」と叫びにも似た感情がいつも内在していたことを、今も鮮明に思い出す。
「幼稚園に行っている間にまた病院に帰ってしまうのでは?」「もしかしたら死んでいるかも?」と考えると怖くて、毎朝なかなか幼稚園に行けずにいた。
それを母は察してか、自宅にいた退院期間中は何かと用事を作って私を早退させ、母子で過ごす時間を少しでも多く作ろうとしていた。
夜は夜でまた母のことを想って不安で寝付けずにいると、布団の中で手をつないでくれたのを思い出す。
天理高校に進学し柔道部での寮生活を始めたので、母との暮らしは15歳までとなった。
入寮の日、父に「母の死に目には会えない覚悟で行け!」と言われた。
はからずも実際そのようになった。
しかし母とは偉大なものである。
たくさんの愛情と温もり優しさを短い人生かけて私に残していってくれた。
また、「不安」という感情を母は、まざまざと私に教えてくれた。
お蔭で私は、常に危機意識を持つ性分となった。
行く先に不安を持つから何事にも慎重に対処し、綿密に対策を練って歩んでこれた。
母によって作られたこの性分は、社会を生きて行くための強みとなった。
今でも毎日あれやこれやと危惧して不安になる。
不安が現実とならないように対策をして、一つ一つ不安の芽を摘み取っている。
それでもまた不安は芽を出す。
どこまでやっても、いくつになっても不安が消える日は無いだろう。
私の人生は生涯、「不安の哲学」と共にあると思う。