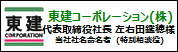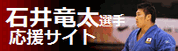2013年
9月
28日
土
目立ちたがり屋

先般、母校の学生約十数名と会う機会があった。
食卓を囲みながら色々と話す中で、気づかされることが沢山あった。
驚いたことに、ほとんどの学生とは初対面だったのに、なぜか多くの学生が私の事を知っていた。
というのは会食が決定後、彼らは事前に私の事をHPやブログなどを見て下調べしていたのである。
我々現代のビジネスマンにとってそれは当たり前の事だが、自分のバンカラ学生時代と比べれば、今の子達はなんと洗練された身のこなしだろうと感心した。
今の時代、ITは人の暮らしやコミュニケーション、そしてビジネスに必要不可欠なものとなっている。
世の中がこんな風になる30年以上も前から、私の師匠である東建コーポレーション㈱の左右田鑑穂社長は、預言者のようにITの重要性を私に教示してくれていた。
30年以上前と言えばまだWindowsなんて存在せず、パソコンは高価で個人はもちろん大企業でも限られた部門でしか購入できなかった超アナログ時代。
そんな時代から東建コーポレーションの前身である東名商事の本社には、試験運用段階ではあったが、もうすでにコンピューターが存在し、社長はITの今後の有効性をたえず語られていた。
左右田社長のお話を聞かせて頂きITの有効性を感じていたものの経済的な問題もあり、当社がパソコンを導入したのは、社長に遅れること十数年以上後であった。
その後、当社は名刺の延長線上程度の簡単なものではあったがHPを製作した。
その当時は中小企業の製造業者でHPを作っていた会社は少なく、「問屋さん相手の商売で、なんでそんな物がいるの?」と不思議がられたり、私が若かったせいもあったのだろうが「目立ちたがり屋」と冷笑を浴びせられた事もあった。
また「ほかにすることがもっとあるだろう」と、年配の中小企業の社長にはお叱りまで受けた。
その後、当社のITの転機は今から約8年前。
左右田社長から「立花、次の段階を視野に入れるのならWebを今よりもっと充実させる事だ」とご指導頂いた事が、きっかけだ。
それを機に、名刺レベルの情報量であったHPの内容を充実させ、より詳細で新鮮な情報を発信するように努め、リニューアルを繰り返している。
その成果は確実に出ており、情報発信量の増加に伴い年々、ビジネスチャンスや取引先が増えている。
また本年度からはまだ1名ではあるが、4月よりWeb編集室も設けて、更なる情報発信を心掛けている。
最後に一つ、前出の学生達との会話の中で気になったことがあった。
学生達は就職先を選ぶ際にも、Webを通して様々な情報を収集し、就職先の取捨選択をしているとのことであった。
決して大手企業ばかりを選り好んでいる訳ではないが、情報量が少ない企業を就職先に選ぶのは二の足を踏んでしまい、情報量の多い企業から選択しようとすると結果的に大手企業が候補に残る、との事であった。
これは消費者の心理とも共通する事柄であり、我々中小企業の経営者も真摯に耳を傾けなければならない声だと思う。
情報の発信そして発信の積み重ねが、いかに大切かを再認識させられた出来事で有った。
2013年
9月
21日
土
たえず見直す

私の第二の座右の銘である「たえず見直す」という言葉を、いつもよりもう一段掘り下げて考察してみた。
昨今の社会全体の仕組み、制度、組織、会社等を見渡すと、世の中の変化に対応出来ず、「時代遅れ」になってしまい、それが原因となってシステムエラーを起こしている事例が実に多くなってきたように思う。
その当時にはソレが、確かに最良であり最先端であったのだろうが、しかし時が流れ世の中が変化しても尚、時代遅れの構造やシステムを只々運用しているのをよく見かける。
たとえば会社単位で例を出すと、見直しをおざなりにして旧態依然のまま、扱う商品の変化もなく、長年に渡り営業活動の内容を変えることもなく、その結果、時代遅れになり、最後にはジリ貧に陥り、倒産や廃業を余儀なくされた会社をいくつも見てきた。
現在、日本では社会の構造改革が叫ばれているが、「社会」とは会社など組織全般の集合体である。そして「会社や組織」とは、私たち個人個人の集まりである。
それゆえ一人一人の確固たる意識改革からスタートしなければ、社会の改革は進まない。
一人一人が改革に目覚めて精進することによって、ひいては会社や組織に貢献し、その貢献が最終的には社会の利益に結びつくと思う。
・・・と話が大きくなってしまったので、もっと現実的な話に戻そう。
目まぐるしく変化し続ける現代では、昨日までと同じ事を忠実に続けていれば会社は存続出来るという時代では、もうなく、会社も時代に合わせて変化して行かなければならない。
繰り返すが、会社は個と個の集合体であるから、一人一人が改革を意識しなければならない。
「改革」の手始めは、身近な所の「見直し」である。
現状に甘んじることなく、どうすればもっと良くなるのか、問題点はないか、無駄はないか、たえず見直すこと。
そして時代の変化に気づくこと、その変化に合わせて行動することなどが大切だろう。
どこの組織や会社等においても、構造改革が必要なのは分かってはいるだろうが、実際に改革するとなると言葉だけが独り歩きして、遅々として進んでいないのが現状ではないだろうか。
見直し事や改革は、新しく何か事を起こすより大変な労力と時間を要するが、しかしそのまま放置することは怠慢であり妥協である。
怠慢や妥協を重ねた先には、会社の「倒産」という「奈落の底」が待ち受けていることを、経営者は肝に銘じなければならない。
2013年
9月
13日
金
社会的に存在意義のある会社

先般たまたま夜中にテレビを点けると、種苗会社で開発を担当さてる方のドキュメンタリーを放送していた。
私の座右の銘である「諦めず気が遠くなるまで繰り返す」と通じる部分もあり、大変感銘を受けた内容だったので、ここで紹介したい。
年に一度しか実らない収穫物の中から優秀な種苗を、特性(耐寒、耐暑、病害、降雨量、収穫量等)に応じて選び出し交配させ、また翌年も、さらなる優秀な種苗を作り出すために交配と選抜を繰り返す。
またその次の年も、その次の年も、その次の年も、その次の・・・
そのように気が遠くなる程の膨大な時間をかけ、幾度も繰り返すことで優秀な種苗を作るのである。
すぐには成果が出ない地道な作業である故、信念が無ければ、続けて行けない仕事であろう。
しかし、もはやこの開発者にとって仕事とは、「生計を立てる手段として従事する労働」ではなくなり、この開発者は「人類に貢献する」という使命を果たすために、仕事をしているように見えた。
というのは、「最終的には、この種苗を中国大陸へ持っていき、あの広大な大地に埋めてみたい」というのである。
なぜならば、日本は国土が狭く耕作面積は狭いが、優秀な種苗があるので収穫量が高い。
それに比べ中国は国土が広く耕作面積は広いが、優秀な種苗が無いので収穫量が低い。
だから優秀な種苗を中国大陸に持ち込み、あの大地で育めば莫大な収穫が見込め、今後の人口爆発による人類の食糧危機、そして飢えに苦しむアフリカ等の後進国の飢餓に貢献することが出来ると言い切るのである。
実際は国と国との利害、駆け引き、民族の価値観や思想背景の違いによる国民性、コピー品種の問題など、諸問題のハードルは高いが、それが実現すれば、必ずや「人類の食糧危機と飢餓」に貢献することが出来るであろうと私も思う。
それにしても、私が最も関心がわいた事は、社員がここまで「遣り甲斐」と「使命感」そして「信念」を持って仕事に打ち込める環境を提供しているのは、いったいどんな経営者なのだろうか?という事である。
私の目標の中に「我が社を、社会的に存在意義のある会社、働く価値のある会社にする」というものがある。
これをもっと具現化する為にも、開発者本人や経営者の方に、質問したいことが山のようにある。
是非ともお会いして、教えを乞いたいと痛切に思っている今日この頃である。
2013年
9月
05日
木
リスク分散について

当社の主力商品を大まかに分類すると、寝装寝具類(繊維)と環境土木産業資材(土木)がある。
建築関係のお得意さまからは「なぜ土木資材の会社が、官公庁向け災害用毛布を売っているのですか?」とよく聞かれ、繊維関係のお得意さまからは「なぜ繊維の会社が土木資材も売っているのですか?」とよく聞かれる。
これには訳があって、父の会社である繊維関係の会社と、私が立ち上げた会社である不動産(当時)&土木資材の会社、これらの会社を合併させた結果なのである。
父が高齢になった為、私が父の会社の事業も引き継ぐことになったのだが、その当時の繊維業界は需要と供給のバランスが崩れておりマイナス成長の時期であった。
そのため繊維事業の会社との合併は、不採算部門を抱えることと同じであった。
しかし不動産(当時)&土木資材の事業は黒字だったため、繊維事業を回復させる為の新たな設備投資をする事が出来た。
その一つを例に出すと、真空パック包装機を導入した。
それにより災害用などの長期備蓄出来る毛布を販売することが可能になり、繊維部門も息を吹き返し始めた。
そのうち「クリーニング事業を譲渡したい」という話が外部から来て、新たにクリーニング事業も始めることになった。
それを機に、私は「製造」に「サービス」の付加価値を付けることを考え、今までは販売したらそれで終わりだった毛布を、使用後に再びお預かりし、クリーニング加工したのち再真空パック処理を行い、元の状態に戻して購入者の元に返すという製品のライフサイクルに合わせた事業を開始した。
それにより業績が上がり、合併当初は不採算部門であった繊維事業が、今では土木建材部門を超え当社のメイン部門となった。
私は長期安定経営を目指すには各部門の見直しや開発と共に、多角経営は必要不可欠と考えている。
どの業界にも景気のサイクルはあり、良い時期と悪い時期はあるものだが、単一事業だとマイナス成長期に息切れしてしまう可能性がある。
しかし多角化経営であれば、苦しい時期にはプラス部門が会社を支えてくれるし、マイナス部門にテコ入れをし、同業他社と差別化を図る余力もある。
また1年単位で考えてみても、業界により繁忙期は異なるので、ある部門が端境期で人員が余っても、余った人員を援軍として繁忙期の部門に配置したりもできる。
しかし単一事業であれば、繁忙期に派遣を雇ったり、端境期には人件費がコストを圧迫したりするだろう。
ところで当社は介護付き賃貸住宅を運営する予定で現在開設準備中である。
本業とは関連のない新規事業なので驚かれることが多いが、ノウハウを充分に持った会社及び有資格者との提携業務である。
この新規事業も私の「不安」を少しでも取り除いてくれるリスクマネージメントなのである。
会社を支える柱は多い方が安心だし、リスクを分散出来る。
しかし柱を増やす為に、社運を掛けるような最大限のパワーを使うことは、してはならない。
新規事業計画は、軌道に乗るまでの期間や万が一の事も考慮して、余力を残して行うものである。
ちなみに当社の事業部門の変わり種で、エステテックサロンがある。
「なぜ美容と真逆とところにある社長が、エステを?」と、私の顔を見つめながら質問される事が多く、居心地が悪いのでついでに説明しておく。
エステは私の妹が独立し開業しようとしたのであるが、その際に女性一人では銀行から資金を借りられなかった為、渋々当社のリラクゼーション事業部という形にした。
赤字が続けば早々に撤退さそうと考えていたのだが、会社という形を取っている為、個人店では出来ないような思いきった戦略なども出来た結果、開業して以来一度も赤字の月は無く、予想外に会社に貢献してくれている。