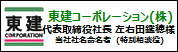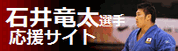2013年
8月
30日
金
経営者に終わりは無い

先日、人間ドックに行ってきた。
PET検査やCT・MRI検査などの精密検査を年に1回、その他にも内視鏡検査や超音波検査は半年毎、あと簡単な内科診察も含めると年に4回は、人間ドックの病院に行っている。
3年前に、健康管理のサポートをしてくれる会社の会員になった。
それまでは命と健康は永遠で無料と考えていたが、今は健康の維持にも「努力が必要である」と考えている。
バリウムを飲まされたり、麻酔を打たれたり、内臓に空気を入れられたり、ルームランナーの上で走らされたりなど、楽しい事は何一つとして無いので、本当は行きたくない。
しかし健康管理も経営者の重要な仕事の一つだと自分に言い聞かせて、検診時期の案内が届く度に、重い腰を上げている。
基本的には、経営者の心身が共に健康である限り、経営に終わりは無いと思う。
しかしその反面、怖いことに経営者の意思と怠け心により、会社経営を終わりにしてしまうことも可能なのである。
経営者にとって「自分は、いつまで経営を続けられるか?」は、絶えず頭の中に浮かんでいる課題であろう。
ところで先月受けた取材のプロフィールに、趣味を記入する欄があったのだが、困ってしまった。
私は好奇心が旺盛な方なので、過去いろいろとチャレンジしてみたのだが、何をやっても長く続かない。早いものでは一回限り、長くてもほとんど1年未満である。
私は俗に言うところの典型的な「飽き性」「せっかち」「短気」なのである。
だから趣味と言える趣味がない。
しかし無趣味にもメリットがある。
経営者の格言で「趣味の時間を持ちたいのなら、経営を諦めるしかない」という言葉が有るが、この課題は自身の性質が幸いして、無理せずクリア出来ている。
こんな何事も長続きしない私であるが、経営だけは別だ。
師匠である左右田社長が常々よりおっしゃられる「七転び八起き」の精神と、私の座右の銘である「諦めず気が遠くなるまで繰り返す」の実践で、挫ける事なく本年で約32年間、おかげさまで経営を続けさせて頂いて来ている。
今後も命の有る限り、続けさせて頂く覚悟である。
まさに経営は私自身にとって人生そのものであり、会社は肉体そのものなのである。
しかしこれとて、心身の健康があってこその話だと思うのだ。
健康管理は仕事の一環。
そう思い、ダイエットも続けていく所存である!!!?
2013年
8月
23日
金
何のために働く?

何のために働いている?
そう聞かれると大半の人は、自分や家族の為に働いていると答えるだろう。
なぜ努力するのかと聞かれたら、自身を成長させる為とか、自身の評価を上げる為などが大半であろう。
私は経営者なので上記の理由に加え、会社を存続させ続けるために努力するし、社員たちに対する責任があるので彼らの暮らしを守って行く為にも一生懸命に働いている。
経営者は会社を考え、社員は自身自分の将来の事を考え、最大限の努力をする。
それで良いと思う。
しかしより会社を磐石なものにするには、この会社が社会に存続する価値が必要である。
また報酬以外にも、社員がこの会社で働く価値が必要である。
その為に必要なのが企業理念である。
会社とは個と個の集合体である。
集合体になると、組織の秩序を保ち方向性を示すためには、理念が会社の大小に関わらず必要となってくる。
また理念を示す事によって目標意識が明確となり、共通の目標を持つことで全員が一丸となり、チームワークが生まれてくる。
チームワークが生まれると次にはプラスのスパイラルが起こり始め、良い意味での個と個の切磋琢磨が生じ、組織の更なるポテンシャルアップにつながるのである。
また理念を社員に示すことにより、自分の会社は社会にどのように役に立っているのかが見え、この会社で働く意味が見えてくる。
私自身も、なぜ会社を存続させたいのかを再認識出来る。
しかし経営者一人が理念を唱えたところで、社員に浸透しなければただの空理空論である。
何度も何度も繰り返して伝えることが、社長の役割であろう。
そして社員がポテンシャルを最大限に発揮できるように手助けすること、その環境を作ること、そして社員がこの会社で働くことにより社会的存在価値を感じられる会社にする事が社長の任務なのであろう。
|
<当社の企業理念>
丸竹COの最大の目的は、すべての社員が物心両面で豊かな生活を送り、自分の将来に安心感を持てるようにする事である。
それが丸竹COの精神「三方良し」の根幹です。
|
2013年
8月
16日
金
明日死ぬ・永遠に生きる

私は仕事を翌日に持ち越すことが、嫌いだ。
その日の仕事を翌日に持ち越すと、「怠惰な自分」に「経営者である自分」が負けたような気分になる。
終業時間が「仕事の終わり」ではなく、夜中の1時2時になろうともその日するべき仕事を全て終えた時が「仕事の終わり」だと私は思っている。
もちろん社員たちには労働基準法が適用されるので、そんな理不尽な事は要求しないが、私は社長であるが故、終わりでないことも終わらせてしまうことが出来る危険性がある。
だから自分を律する為にも、その日の仕事はその日に終わらせる事を自分に課している。
そんな風に生活していると、仕事と睡眠以外の事は何もしてないような気分になって焦燥感に駆られるのだが、それは私以外にも多くの人が感じている事だろう。
昔に比べて現代は様々な技術革新に伴い進歩した結果、非常にやることが増え、現代の社会は多忙になったと思う。
しかし、この忙しい現代社会において時間をいかに有効に使うかが、人生を成功に導くかどうかの決め手になると言っても過言ではないと思う。
まさにことわざ通り「時は金なり」である。
ところで私が仕事と睡眠の次に時間を多く費やしているのは読書である。
私は高校時代に柔道を頑張りすぎて、授業中は寝て過ごしたので(笑)、その反動もあってか、知識に対する欲が人より高いと思う。
会社を繁栄させ、100年先にも続いているような長期安定経営を実現させる為には、もっともっと多くの知識を吸収し、色んな事に精通しなければならないと考え、出来るだけ読書をするように心掛けている。
ある本の中に書いてあったアメリカの哲学者の言葉に、「毎日一時間、学習(読書を指す)するだけで、一年たてば彼はその専門家になれる」という言葉があった。
一日にたとえ一時間でもいいから毎日、自分にプラスになる知識を吸収しようとする努力は、人を成長させるであろう。
毎日忙しいとはいうものの、無駄に過ごしている時間はだれしも絶対にあるはずである。
無駄に過ごす時間が多ければ多いほど、平凡に人生は終わってしまうのではないだろうか。
私は自分自身の人生を平凡には終わらせたくないと考えている。
けれども何もしたくない気持ちになる時もあり、そんな時にはこの言葉を思い出す事にしている。
「明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい。」
マハトマ・ガンジーの言葉である。
2013年
8月
07日
水
お知らせ
日本最大の経営者ウェブTV「大阪の社長TV」に取材をして頂きました。
番組では「母に教わった不安の哲学」「製造業に付加価値を付ける」「自ら示す社員教育を」「百年続く会社へ」
以上の4つのテーマについて、お話をさせて頂きました。
本来このような緊張する場は苦手なのですが、「これからの日本経済を支える熱く有望な若者と地域に対して企業トップのビジョンや価値観を直接発信できる唯一の地場メディア」だという事、そしてこの番組に私を推薦して下さった方々がいらっしゃるとの事をお聞きし、出演させて頂きました。
推薦して下さいました方々、取材して下さいました社長TVスタッフの皆様、ありがとうございました。
※画像をクリックすると番組に飛びます。
2013年
8月
02日
金
お節介な人ほど有難い

約30年に渡り事業をさせて頂いてきた中で、特別思い出深い営業マンがいる。
「仕事に関して言えば、お節介な人ほど有難い存在なのだ」と、私が思い至るようになったきっかけの人だ。
25年ほど前だろうか。
私が駆け出しの社長だった頃、その人もまた入社まもない駆け出しの営業マンだった。
インターネットなどまだ無い時代である。
例えば仕様書やパンフレットなどを作成するにしても、外注する資金は当時の我が社にはなく、素人同然の私一人の構成で、ワープロとコピー機を使い作成し、一社一社に郵送していた。現在の何倍もの時間と労力をかけた、まさに「手作り」の資料だった。
そんな資料を私が発信する度に、例の営業マンはすぐさま電話を掛けて来た。
「社長!また間違ってるで!!」と。
数度の話ではない。
何回×100も電話を掛けて来るのである。
それは誤字脱字や表現の間違い、見解の相違など、過去に発行したパンフレットに至るまで何かを発見する度に、電話を掛けて来てご指摘を下さるのである。
電話が鳴るたびに「またあの人か!?」と思わず身構えてしまうほどである。
誰も気付かないぐらいの小さな間違いをわざわざ連絡して来て「ほんまにお節介な人や」と迷惑に思っていた。
それどころか、もしかしてミスを指摘するのが趣味なんじゃないのか?!と疑ってすらいた。
かと言って、指摘された箇所をそのまま放置するのは、彼から逃げたような、そして彼に負けたような気がするから絶対に嫌であった。
彼から指摘の電話があると、私はほとんど戦いに挑むような気持ちになりながら、その日のうちに夜を徹して資料を作り直す。
そんな事を幾度と無く続けていたのである。
だからその営業マンに対して「なにくそ!!負けるものか」と執念を燃やしても、感謝の気持ちはどうやってみても持てずにいた。
ところがである。
彼は、次々と当社の商品を売ってくれるのである。
そして数年経たずして、彼は当社の製品のトップクラスのバイヤーとなった。
彼は当社が発信する資料を徹底的に精読し、製品を完璧に把握していた。
だから彼はお客様のどんな質問においても、即座に正確に回答することができた。
そうして次々と信頼を得て、おのずと売り上げも向上して行ったのである。
なぜ気付かなかったのだろう!彼は私の手作り資料を誰よりも熱心に読み込み、真摯に向き合ってくれていたのだ。そして中途半端なものをお客様の前に出したくないというプロフェッショナルな想いから、何度も何度も私に指摘を続けていたのだ!
それに気付いた時、私は初めて心の底から彼に感謝をし、彼の行為を迷惑だと思っていた自分を恥じた。
出会った頃は駆け出しの営業マンだった彼は、昇進を重ね現在は役員となられた。
当社の有力なお取引先である。
今でも年に1、2度、お話をさせて頂く。
いつも会話の最後はこの話になり「私の訂正要求や指摘もかなりしつこかったけど、食い下がってすぐに更新してくるあんたも、しつこかったなぁ!」と昔を思い出して笑い合うのである。