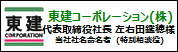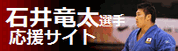2013年
6月
28日
金
歴史のリーダー達から学ぶ

私は、私の師匠である左右田鑑穂社長の著書はバイブルとしているが、それ以外のビジネス本は読んだためしがない。
なぜならばリーダーの姿や組織作り、戦略などは、失敗も含め歴史本から全て学べるからである。
私の趣味の一つに読書が有るのだが、戦国時代の歴史物を読むことが多い。
中でも特に信長、秀吉、家康、が大変おもしろく学ぶところが多い。
ご存知の通りこの3人の功績により、戦国時代各地に点在していた勢力が統一され、近代日本の基礎が形づくられたのである。
この3人が生きた時代の変化を「会社の形の変化」、そして3人のリーダーを「一人の社長の変遷」に置き換えてみると、社長の役割や組織作りのヒントが見えてくる。
そのことを左右田社長は「成功へのアドバイス」の中で述べられている。
まず、何もない所から形(会社)をつくった織田信長。
信長は、自が先頭に立って行動してみせ、強い牽引力で皆を率いて行くリーダーであった。
そして造られたもの(会社)を広げた豊臣秀吉。
協調性があり、根回しや懐柔が得意で人を使うのが上手いリーダーであった。
そして広げたもの(会社)を、より強固なものにした徳川家康。
人を育てるのが上手く、組織作りがうまく、マニュアル化することにより長期安定政権の基礎を築いたリーダーであった。
こうして見てみると、会社の変化と共に、求められるリーダーの形も変化して行くのが分かる。
今の私をこの三人に当てはめてみると、信長に近い秀吉ってところだろうか。
経営者として約30年の年月を経て、体力的な理由もあり、最近ようやく何とか人を使うことを覚えてきた。
しかし秀吉のままでは先細りしてしまう。家康になる必要がある。
家康は、幕藩体制により地方分権をし、地方のことはそれぞれの大名たちに任せていた。
任せられると大名たちも一層責任感を持ったであろうし、自分の藩を発展させようと努力したであろう。
何でもリーダーが決定するのではなく、任し、権限を与え、責任を待たせる。
それが人を育てるということでもあるだろう。
会社が業績を上げて発展していく為には、「人を適材適所に配置して上手に使うこと」、そして会社を永続させるには「人を育てること」が大切である。
また徳川幕府は、拡張主義に奔らず内政の安定に努めることにより、長きに渡り政権を保った。
結論としていま私が考えていることは、今後やみくもに年商を伸ばすことだけに注力するのではなく、長期に渡り安定経営を保つということである。
人を育てる能力が長期安定経営の必須条件であること、そしてそれが我が社の今後の課題であることを私自身が肝に銘じて進むべきであろう。
・・・と、ここまで書いた事と相反するかもしれないが、私の経営理念としてはやはり「まず自分が先頭に立って一番働くこと」である。誰よりも働くリーダーの下であるからこそ部下は自ら動くのであり、先頭に立つリーダーの姿を見て部下は育つのである。と私は思っている。
いきなり家康にはなれない。
まずは信長から。そして秀吉、家康へと、私も含め社員一人一人が変化して行かねばならない。
2013年
6月
20日
木
母とピンクと私

母は苦しい闘病生活と向き合いながらも、沢山の愛情を私に与えてくれた。
小さい頃には「悪ガキ」、小中時代には「問題児」、高校時代には「過激派」で、周りの大人達の手を焼かした私だが(笑)、母に対してだけは常に従順であった。
しかし一つ、毎回すごく嫌だった事がある。
それは母がいつも私にピンクやフリフリや花柄の可愛い服を着せようとした事である。
それが嫌で堪らなく、泣きながら押入れの奥に隠れて布団にしがみ付いていた記憶が有る。
そんな事が高校時代まで続いた・・・とかではなく、幼い時の話であるから、今の私のゴリラのような顔で想像するのは、お止め下さい!!
母は女の子が欲しかったせいもあって、私に女の子用の洋服を着せていたのだと思うが、母の想いとは裏腹に私の図体はグングンとデカく成長し、私の魂は男男しい物や人に魅かれ、結局15歳で親元を離れ、天理高校柔道部に行き日本一を目指す道に進んだ。
ピンクとは真逆の世界である。
高校時代に母が病をおして何度か試合を観に来てくれたことがあった。
後に父から聞いた話である。
母は私の試合を観戦中ずっと、指輪が曲がるほどの力で拳を握りしめていたせいで、指には紫色の指輪の痕が出来、またある時は強烈に歯を食いしばっていたせいで、差し歯が抜けてしまったそうである。
あのひ弱な母の体の何処にそんな力があったのであろうかと思うが、母は客席で体力と気力の限りを尽くして、私と共に戦っていてくれたのであろう。
精根尽き果てた母は毎回、応援から帰ると食事も満足に食べられなくなり、2週間くらいは廃人のように寝込んだそうだ。
母の愛情は海よりも深いと言われるが、こうして思い出すとまさにその通りである。
自分の寿命を縮めてまでも、私を力づけに来てくれていたのである。
母が亡くなってすでに三十数年が経過しているが、今でも思い出すと涙が出そうになる。
そしてピンク色の服に身を包む自分の写真を見て、吹き出しそうになる。
立花克彦 幼少時の写真

2013年
6月
15日
土
真実の付き合い、実用の付き合い

ただの知り合いというだけで、安易に物事を他人に依頼しようとする人がいる。
また何か頼み事がある時にだけ、連絡を取ってくる人がいる。
「持ちつ持たれつ」と言う言葉があるがそうではなく、一方的に自分のしてほしいことや、やりたいことばかりを主張する人を多々見受けるようになってしまった。
昨今の日本の風潮を見ると、「侘び」、「寂(さび)」、「控え目」、「謙虚さ」、「礼儀」を美徳とし、またアイデンティティーとして生きてきた日本古来の思想と良さが失われつつあるように思う。
ところで、異業種交流会の席で興味深い話を伺った。
世間から「鬼才」と評されるほどの凄腕社長の逸話だ。
その社長は中小規模の出版社の社長なのだが、PCの爆発的な普及により、紙書籍が減少しつつあるこの時代においても、劇的に業績を伸ばしているそうだ。
この話には、登場人物がもう一人いる。
気難しい大物作家だ。
この作家の出版元になるのは、大手出版社であっても至難の業で、入れかわり立ちかわり数多くの出版社が何度も依頼しに来ては、その度に足蹴にされているらしい。
ところが先に紹介した社長は、初めての対面で、しかももほんの数分で、この大物作家の出版元になる了承を取り付けた。
あの気難しい作家を、いとも簡単に「YES」と言わすとは!
世間は驚いて、この話は随分と話題になったらしい。
なぜこの社長は、大物作家をあっさりと懐柔出来たのだろうか?
そこには、こんな裏話があった。
社長は、その大物作家がデビューしたての頃から、作品が発売されるたびに購入してはその感想を手紙ににしたためて送っていたらしい。約20年以上に渡り毎回必ずだ。
社長と作家が対面したのは、この時が初めてであったが、きっと二人の間では旧知の親友が如く通じ合っていたのであろう。
ここから先は私の想像だが、その社長は「いつか出版元にしてもらおう」との下心があって20年間以上も手紙を書き続けていた訳では無いだろう。利害など関係なく、ただ気持ちを伝えたかっただけだろう。
それこそが「真実の付き合い」だと、私は思う。
反対に、用事がある時にだけ付き合いをするのは「実用の付き合い」とでも呼ぼうか。
用件が有っても無くても日頃からこまめに顔を出したり、、時候の挨拶で近況を伺ったりする。
そうする事で、私はあなたを気にかけていますという気持ちが言葉に出さずとも伝わるものだ。
そのような「真実の付き合い」をしていれば自然と信頼関係も出来上がる。
そういう間柄であれば、何か頼み事をされても、「この人の頼みなら」と、損得なしに快く受け入れる気になるものだ。
私は、勉強になる話を聞かせてもらった時や、初対面の人と会って意気投合した時や、忙しくて会えないけれど忘れずにいるという事を伝えたい時など、手紙を書いて送るようにしている。
手紙と言っても、仕事の合間に書くので短い文章でハガキだったりするのだが、とりあえずその時の私の気持ちを書いて送っている。
そうする理由は、「真実の付き合い」をしていたいからである。
2013年
6月
06日
木
体育会系新入社員

昨今、体育会系出身の新入社員の需要が再び高まっているらしい。
私が学生時代に身を置いた奈良県天理高校は全寮制の学校であった。
そして柔道部専用の寮があり、1年、2年、3年生が各1名ずつ計3名の相部屋と決められていた。
その為、柔道の練習中だけではなく、24時間体制で厳しい上下関係の中にあった。
言葉使い、挨拶の仕方に始まり、掃除の仕方、礼儀、団体生活での協調性やマナーまで徹底的に教え込まれる。
また私の所属していた柔道部は全国優勝を目標に掲げている部であった為、誠に厳しい練習の日々であった。
私は2度の全国優勝を経験したが、そこに至るまでには全身全霊で努力をしたし、物凄く苦しかった。
お蔭であの時以上に苦しいことは未だに無いし、社会に出てから心底辛い事があっても「あの当時の練習に比べればマシだな」と思って気持ちを持ち直すことが出来ている。
私自身の話に反れてしまったので話を戻すと、体育会系出身者は入社する前からすでに礼儀や、組織の中の上下関係を学んでいるし、目標達成の為に努力する姿勢や、厳しい状況にも挫けない強い精神力など、社会人として必要なものを身につけている者が多いと思う。
また団体スポーツを経験した者はチームワークの大切さをよく知っている。
チームが優勝するためには、1つの目標に対して全員が一丸となって一人一人が我を捨て、いかにチームワークを保つかがカギになる。
レギュラー選手は、プレッシャーと戦いながら皆の想いを背負って戦うし、補欠の選手たちは陽の当たらない環境であってもチームに貢献しようと裏方の仕事を進んで引き受ける。
会社はチームであり組織である。
ということは対外的に厳しい競争社会を企業として生き残るために必要なのはやはり第一がチームワークである。
スポーツを通して集団生活を経験した者は、組織としてのチームプレイ全般をほぼ全て身に付けているのである。
従って学生時代にスポーツで切磋琢磨した人間は社員教育をすでに済ましてきているのと同じで、即戦力として戦線に立てる貴重な人材である。
昨今、体育会系学生が再び脚光を浴びだしたのも、厳しい経済情勢と相まって必然的な流れであろう。
とは言っても会社という組織は多種多様な人材によって構成されなくては柔軟になれず、社会の変化に対応出来ない。
様々な能力を持った人材が集まり、それぞれが自分の力を最大限発揮出来てこそ会社の成長はある。
組織作りとは、誠に難しいものである。