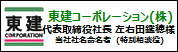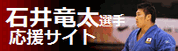2013年
5月
30日
木
神様からの定期便

私は自動車運転免許の更新で、今度こそ「ゴールド免許」だと思い更新申請を毎回楽しみにしている。
しかし未だに「ブルー免許」である。
自慢できる話ではないが、ゴールド免許の制度が出来て以来、未だに1回もゴールドになった事が無い。
何故かというと4年おきくらいに必ず交通違反を犯してしまうからである。
「ゴールド免許」が近づいてくると必ず取締りを受けるので、その頃になるとどこかで誰かに見られているのかなぁとさえ毎回思う。
毎回毎回、更新期限ギリギリに取締りを受けるのである。
記憶をさかのぼると前回は携帯電話だったし、その前は信号無視、その前はスピード違反で、そのもう一つ前はシートベルト。
この偶然の一致、この規則性は、いったい何なのだろうと?とある時、考えたことがあった。
そこで自分なりに思いついたことが有る。
この偶然の一致は、私が前回の違反を忘れて気が大きくなった頃に、神様が警察の方を通して、「気を抜くなよ!安全運転しろよ!」と教えてくれているではないだろうか?
そんな風に頭で考えながらも、アクセルを踏んでしまうのが私の悪い所であるので、
やっぱりこの度もゴールド免許を目前にして、また捕まってしまった。
高速道路での22キロオーバーのスピード違反である。
やはり神様は私を見ていた。
神様は私を見逃してはくれず、「これぐらいだいじょうぶ」と思う私の甘い考えを叩きのめしてくれた。
違反切符を書きながら、この「神様からの定期便」の話を警察官の方達に話すと、「そう言って貰うと大変嬉しい。遣り甲斐がある。」と大層喜んでもらえた。
最後は敬礼で車を送り出して貰った。
捕まったというのに私自身も嫌な気分ではなかった。
考え方一つである。
不愉快なこともその不愉快な事が起きる理由を考えて、自分への戒めだと思うことで感謝出来る。
余談だが「大切にしていた物をなくした」「記念のお皿が割れた」だから「不吉だ」と言うような話を聞く度に、私は「本来なら怪我をしていたかもしれないところを、その大切なものが身代わりになってくれた」「だから縁起が良い」と言っている。
考え方一つである。
正解のない答なら、良い方に考えるほうが上手くいく。
2013年
5月
23日
木
20年越しの「いたずら」

天理高校に在学当時、倫理社会担当で益田多鶴子先生という女性がいた。
その先生の3学期最後の授業は私の中で生涯忘れがたいものとなった。
それは松尾芭蕉の「奥の細道・月日は百代の過客にして・・・」の解説を折り込んだ授業だった。
簡単に書くと、世の全てのものは移り変わり、いつまでも同じものはないという「無常」についての内容だったと思う。
そしてその授業の最後に先生は「人の心は移ろい行くものなので、今日こうして授業を受けたことも、きっと皆さんは忘れてしまうでしょう。もし忘れてなければ20年後私に手紙を下さい。でもきっと手紙は来ないでしょうね。」と先生がおっしゃった。
それを聞いて私の「いたずら心」に火が付いた。
20年後の1999年に必ず手紙を書いて先生をビックリさせてやると、ほくそ笑みながら決意した。
天理高校の校章が梅の花だったので梅の花が咲くころになると必ず先生との約束を思い出した。
月日が流れ、なめ猫とやらが流行したり、バブル景気が始まったり、冷戦が終結したりしながら1980年代が終わったが、私はあの日の決意を忘れなかった。
1990年代に入りバブルが崩壊したり、「のぞみ」の運転が開始されたり、阪神大震災が起こったりしながら時代は移り変わっていったが、私はあの日の決意をまだ覚えていた。
特に最後の365日は、「あと何日」と待ち遠しいほどであった。
そしてついに待ちに待った20年目!
18歳の少年だった私は20年の月日を経て、すっかり中年のオヤジに変貌していたが、先生の反応を想像し、あの授業の日と同じように心の内でほくそ笑んでいた。
学校に先生の消息を確かめると退職されていたが、住所は分かったので手紙を出すことが出来た。
返事はすぐに来た。
「そういわれると確かにそのような事を申したような記憶が有ります。」
「驚きました。あなたのような生徒は初めてです。」と書いてあった。
先生からの手紙を何度も読み返しながら、ようやく20年越しの達成感を得た。
そしてその後、何度か文通するうちに「1度お会いしましょう」ということになった。
20年振りに再会し、互いの近況を報告し合った。
先生は「スリランカの教育を支援する会」を立ち上げ、熱心にボランティア活動をされていた。
私も協力させて欲しいと申し出て、その一端に入れて頂いた。
その年から10年後
スリランカに内戦が勃発して渡航できなくなり、また先生が親の介護を行う立場になられたことも有って、会の解散を決められた。
10年間、微力ではあるが支援させて頂け、会を通して先生と交流させて頂けた。
人の心は移ろい行くものであるらしいが、私の小さな悪戯心は20年間移ろうことはなかった。この話を知人にしたところ、「それはお前が変わり者だから成せた業」という嬉しくない見解をもらってしまった。
ちなみに私の座右の銘は「諦めず気が遠くなるまで繰り返す」である。
ようするに私は、とってもしつこい人間なのである。
左:先生からのお手紙
右:スリランカの教育を支援する会会報誌

2013年
5月
16日
木
便座も積もれば山となる

私の師匠、東建コーポレーション(株)の左右田社長とご一緒させて頂いた時、こんな事があった。
東建と一口に言っても全国に支店があるし、工場も沢山あるし、グループ会社も数多くあるし、カントリークラブや温泉だってある。
その中の一つの会社に社長が訪れた時のこと。
社長が幹部社員に注意を与えている場面を拝見した。
夏場だというのにどのトイレの便座にもヒーターが入っていたらしく、社長はその事について苦言を呈されていた。
断じて言うが、社長はケチなお人では決してない。むしろその真逆の代表みたいなお人だ。
それ故その社長が「小さな無駄」に注意を向けていたことに驚いた。
けれども考えてみれば、真夏の便座ヒーターなど無駄の骨頂。
しかも東建グループ全体の便座の数を考えれば1,000ヶ所はゆうに超える。
「塵も積もれば山となる」である。
小さな無駄と思っていたものは、実は相当な金額の無駄であったのだ。
突き詰めて考えれば無駄な費用を使う事は、お客様の買価にも繋がる。
大企業であればあるほど、小さな無駄でも積もって大きな無駄になる。
いや、中小企業であっても「小さな無駄」を毎日毎月毎年見過ごしていると大きな無駄になる。
左右田社長が苦言を呈されるその場面を拝見し、経営者とはこんな細やかな事にまで注意して日々を歩んでいくものなのだなと重ねて感服し、自らももっと細心の注意をはらい精進して行こう!と心に誓った。
それ以来、それまでは小さな事だからと曖昧にしていたことも、そこに「無駄」はないのか?とたえず見直すようになった。
商売とは面白いもので、1000万円の収入があっても900万円の支出があれば100万円の利益であり、110万円の収入でも支出が10万円なら、利益は100万円で前者も後者も儲けは同じなのだ。
まぁ当たり前の話である。
しかし売り上げを増やす事の方にばかり意識が行き、目の前の無駄が見えなくなっている経営者も少なくはないだろう。
いやはや、かって私もその一人であった。
2013年
5月
08日
水
永遠に売れ続ける物なんかない!

今から6年前に、あのシャープの破錠寸前の今の状況を誰が予測できたであろうか?
当時は液晶テレビの普及の全盛時代で、特にシャープの亀山モデルはシェア№1の大人気を博し、手に入れようと思っても数か月待ちの有様であった。
その後、あまりの売れ行きに増産体制に拍車が係り、地デジ化移行時の楽観的な販売予測も相まって、経営陣が完全に市場に対して錯覚を起こして「永遠に売れるもの」と勘違いをしてしまい、総投資額1兆円ともいわれる液晶工場を建設したのである。
しかし液晶工場が完成する頃には、思いのほか地デジ化買い替え需要が伸びないまま地デジ化移行も終了してしまい、さらには海外の低価格商品の国内大量流入もあり、結局は大きな有利子負債を抱えて稼働しないまま身売りを余儀なくされることになったのである。
そこで私は経営者の端くれとして、また同じ製造業として、シャープの二の轍を踏まない為にもこの問題を自社に置き換えて、その解を考察してみた。
まず高いシェアは強い販売力を持った代理店網が支えてくれるからであり、その関係で競合メーカーが少ない時には参入障壁やコマーシャルの効果で売り手寡占が進みヒット商品となる。
しかし、それは長くは続かないことを経営者は知っておかなければならない。
今の時代、売れるとみるや数か月を経ずして次々に競合メーカーが新規参入してくる。
グローバルになった昨今においては新興国の台頭は著しいものが有り、低価格商品も参入して来る。
そうして品数も増えて選択肢が多くなると、必然的にシェアは下がる。
よしんば価格競争を勝ち抜いて高いシェアを守れたとしても利益は減少する。
そうなる前の戦略として、右肩上がりに売れている時期に「次の一手」として、その商品の差別化を図り価格を下げずグレードを上げて老舗として王道を歩むか、もしくは新規開発商品の投入や新規事業の展開等のスタートをきるべきである。
そのことから考えても「企画」というのは大変重要である。が、中小企業では大手のように単独の企画部を作るのは難しい。
そこで当社では、現場経験者を営業に、営業経験者を現場に配置転換するなどをし、経験を生かした上で新たな視点で企画検討が出来るよう組織作りをしている。
また事業計画は余力を残して行うべきものであり、社運を掛けるような最大限のパワーを使うことは、よほどの勝算が無い限り自重しなければならない。
またどんなに自信の有る事業計画であっても臨機応変に時代の変化に合わせ、「世間体」や「意地」に捕らわれず中止する決断力や勇気が必要である。
経営者は今の時代を生き残るために、事業全体のマクロ的な事から、例えば備品費の節約などのミクロ的なことまで取りこぼしなくたえず見直す遂行力が必要である。
たとえ主力商品であっても、利益を上げている部門であっても、たえず見直す事。
そして永遠に売れ続ける物は無い!と自覚して、「次の一手」を打ち続けることが会社を存続させる為の策なのである。