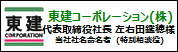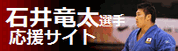2013年
1月
27日
日
不安の哲学

私は元気な母を知らない。
元気に振る舞っていても、母は常に病と隣り合わせに居た。
私の、母の記憶は和歌山市にある日本赤十字病院の病床から始まる。
母は私が生後8か月目に重度の腎機能障害に罹り入院を余儀なくされた。
3年後に退院するも腎機能が落ちていたせいか、今度は銭湯で尿路感染による腎臓結核を患い、その後また約1年間、保菌検査が陰性に転じるまで入院した。
父が「あのとき自宅に風呂が有ったなら」と苦しげに呟いたことがある。
その 時の哀れな想いからなのか、父は「貧乏は罪悪だ」としばしば言うようになった。
しかし腎機能とは怖いものである。
1度悪くなるともう完全に回復するということはない。
臓器の中でも心臓や肺に次いで治療の難しい臓器だそうである。
母は年々、機能が低下していき入退院を繰り返しながら、数年後には腎不全に陥り人工透析を始めるに至った。
これがまた週3回、1回6時間も(亡くなる前は毎日)透析をしなければならず、副作用も酷く、苦しそうにしていた母の姿が、やる瀬ない想いと共に浮かんで来る。
母が亡くなった時、母の姉が傍らで「これでもう透析をしなくてよくなったね」と言ったそうだが、その言葉が忘れられない。
私の、母と暮らした記憶は5才前後から始まる。
それまでは母方の祖父母の家で育てて貰った。
幼少ながらその頃すでに、母がいつ死ぬかもしれないという恐怖が常に身近にあり、「死んだらあかん!!」と叫びにも似た感情がいつも内在していたことを、今も鮮明に思い出す。
「幼稚園に行っている間にまた病院に帰ってしまうのでは?」「もしかしたら死んでいるかも?」と考えると怖くて、毎朝なかなか幼稚園に行けずにいた。
それを母は察してか、自宅にいた退院期間中は何かと用事を作って私を早退させ、母子で過ごす時間を少しでも多く作ろうとしていた。
夜は夜でまた母のことを想って不安で寝付けずにいると、布団の中で手をつないでくれたのを思い出す。
天理高校に進学し柔道部での寮生活を始めたので、母との暮らしは15歳までとなった。
入寮の日、父に「母の死に目には会えない覚悟で行け!」と言われた。
はからずも実際そのようになった。
しかし母とは偉大なものである。
たくさんの愛情と温もり優しさを短い人生かけて私に残していってくれた。
また、「不安」という感情を母は、まざまざと私に教えてくれた。
お蔭で私は、常に危機意識を持つ性分となった。
行く先に不安を持つから何事にも慎重に対処し、綿密に対策を練って歩んでこれた。
母によって作られたこの性分は、社会を生きて行くための強みとなった。
今でも毎日あれやこれやと危惧して不安になる。
不安が現実とならないように対策をして、一つ一つ不安の芽を摘み取っている。
それでもまた不安は芽を出す。
どこまでやっても、いくつになっても不安が消える日は無いだろう。
私の人生は生涯、「不安の哲学」と共にあると思う。
2013年
1月
19日
土
三方良し

「儲けるは欲、儲かるは道」という言葉がある。
たった一文字の違いだが、この両者は違う。
「儲ける」は、儲けることを目的とした商いなのに対し、「儲かる」は、良い商いをしたその結果である。
儲けようと思って作った商品で稼いだ100万円と、買い手の満足を考えて作った商品で稼いだ50万円となら、長い目で見れば後者の方が会社にもたらす利益は大きい。
前者は金額以上の価値は無いが、後者は会社への信用という利益がついてくる。
会社を末永く続けて行くには、「信用」は「儲け」よりも大切なのだ。儲けは後からついて来る。
そのことを、先人の近江商人はこんな言葉で、我々に教えてくれている。
「義を先にし、利益を後にすれば繁盛してもうかる」と。
またこれも近江商人の言葉であるが「三方良し」というものがある。
売り手と買い手がともに満足し、社会貢献もできるのがよい商売であるという言葉だ。
丸竹COが目指しているのも、そこである。
商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献したい。
・・・と書くとまるで優等生の弁のようでむず痒くなるのだが、事実、お金儲けだけが目的の会社が社会に歓迎されるはずがないのだ。
社会に歓迎され信用され続ける会社である為に、社会貢献をする。
そう思い取り組んでいるのが、障がい者の雇用であったり、地域のスポーツ大会への協力であったり、東日本大震災の災害復旧の支援などである。
また最近は地球環境を考慮し、太陽光発電を導入したり、環境に優しい商品開発を心がけている。
2013年
1月
10日
木
素晴らしい執念!!

最初に私の師匠である東建コーポレーション㈱ 左右田鑑穂代表取締役社長の御友人で、メディア事業と広告SP事業の展開をされている㈱中広(CHUCO CO.,LTD.) 後藤一俊代表取締役社長をご紹介させて頂きます。
この社長は、スゴイのだ。
何がスゴイのかは、のちほど書こう。
ところでご存知の通りだが、私は最近ブログを始めた。
私にとってブログは趣味の延長線上であり、また備忘録の一貫だ。
ほとんどの方もたぶんそうであると思う。
もちろん例外として、芸能人がファンとのコミュニケーションツールとして使ってるブログや、企業がPRの為にしているブログや、他にはアフィリエイトを目的でしているブログなどもあるが、そういう場合を除けば、やはりブログは趣味の延長線上であると思う。
趣味ならば、誰からも強制されることもないし、やりたい時にやればいいし、やりたくなければやらなければいい。
だからこそ、モチベーションを保つのは難しいし、例え趣味だとしても、それを毎日欠かさず続けるのは大変なことだ。
しかし、最初に紹介させて頂いた後藤一俊社長は、なんと連続2000日以上、欠かすことなく毎日ブログを更新され続けているのだ。
後藤一俊社長のブログはコチラ。
http://www.chuco.co.jp/blog.html
2000日と言えば、まる5年以上なのだが、その間には、体調が悪かった日や、てんてこ舞いに忙しかった日や、ブログを書くような気分になれない日や、急な予定が飛び込んで来た日など、言うまでもなくあったはずだ。
それでも毎日ブログを更新され続けていらっしゃるのだ。
「毎日」「一日も欠かすことなく」続ける。どんな体調でも、どんな状況でも、どんな気分の日でも毎日続ける。これは本当に凄いことだ。
一日も欠かすことなく5年以上続けていることって、何があるだろう?と自分を振り返って見るが、なかなか思いつかない。
ブログに限らず、「どんな事があっても諦めずやり遂げるぞ!」と決めて、それを実際に実行できる方は、強靭な精神と忍耐、粘り強さと、執念を持っているのだと思う。
私の座右の銘は「諦めず気が遠くなるまで繰り返す」であるが、ブログ連続2,000日達成の偉業を前に敬服するばかりである。
2013年
1月
05日
土
恩師 加藤秀雄先生を偲んで

平成25年1月1日 恩師である天理高校柔道部元監督の加藤秀雄先生が御出直し(お亡くなり)になられた。
天理柔道から学ばせて頂いたことは数限りなくあり、それが今の私の礎となっている。
私が柔道を辞めずに踏みとどまることが出来たのは、加藤先生の情熱のお蔭だ。
私が高校1年生の6月のこと。
入部して2ヶ月目。
あまりの練習の厳しさ辛さに、私はやる気を無くしていた。
どうやって辞めようか、毎日そんなことを考えるようになっていた。
そんな折、気の緩みもあって、練習中に右耳が縦に裂け、8針縫う怪我を負った。
ちなみに反対側の左耳も練習により、ピンポンボール玉ほどに腫れ上がっていた。
私のそんな姿を見た母親は相当ショックを受けたようだった。
当時、私は学校の寮で生活をしていたので、久しぶりに会った私の姿は、母を動転させるには充分だったようだ。
柔道を全く知らず、耳の潰れた息子の姿に心痛する母、柔道から逃げたい私。
私たち親子は退学することを決意して、加藤先生の元へ出向いた。
「やめさせてもらいます。来年、地元の高校を受け直させます。」と訴える母。
しかし加藤先生は首を縦には振ってくれなかった。
加藤先生は「息子さんは天理が責任を持って預かります。保証します。やる気ない者でも闘志のない者でも育てます。それが天理です。」「夏のインターハイが終わるまで様子を見てください。もうしばらく預けてみてください。」と、私を引き止めて下さった。
母も私も加藤先生の情熱と執念に押し切られる形で、再び柔道を続けることになった。
しかし母はやはり私の事が心配だったようで、ことあるごとに「辞めていいからね」と言い続けていた。
夏が過ぎ、たまたま帰省の折りに地元で柔道大会があり(確か淡輪町の町政30周年か・・・?)、私は出場することになった。
その大会で大人も含めた個人戦に断トツの強さで優勝させて頂くことが出来た。
驚いたことに天理柔道に入部してたった数ヶ月で、自分でも気づかぬうちに随分強くなっていたのだ。
母は、その時入院中だった為、大会を観戦することはなかったが、友人から私が優勝した話を聞いたそうだ。
それ以来母は、私が怪我をしてももう何も言わなくなった。
母と二人、加藤先生に退学を申し出に行ったあの時、もしも加藤先生が首を縦に振っていたら、私は沢山の素晴らしいことを知らないままで居ただろう。
あの日、踏みとどまれたのは、先生の柔道への情熱と天理柔道にかける執念があったから。
だから私は先生を信頼し、柔道を続けることが出来た。
昨年、先生の講道館柔道九段昇段の記念品の湯飲みに
続けることの よろこび 九段 加藤秀雄 とあった。
「諦めず気が遠くなるまで繰り返す」ことを教えてくれた先生であった。
今尚、また人生の最後まで先生の御指導は永遠です。
伏して先生のご冥福をお祈り申し上げるばかりです・・・!!