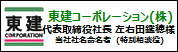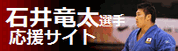残暑お見舞い申し上げます
さて本日2025年8月15日は第二次世界大戦の終結から80年を迎えます。
多くのメディアが連日「平和の尊さ」を伝える中、私の胸にもある記憶が蘇ってきました。
あれは昭和43年樽井小学校3年生の秋頃のことです。
当時、父の勤務していた久紡績株式会社の慰安旅行に私も一緒に連れて行っていただき、広島平和記念資料館を訪れました。
ただ小学生の私は、展示ケースに並ぶ焦げ跡の残る遺品や写真はどこか遠い物語のようにしか思えませんでした。
しかしどうしても目が離せなかったものが一つありました。
それは、原爆の熱で溶けて歪んだガラスの空き瓶の山でした。
そしてそれは私の心を捉えて離さず、大阪に帰宅後「同じような瓶を作ってみたい」と思い立ったのです。
ここから先の行動は、現代では非常識に当たるようなものですが、昭和40年代という時代背景のもと、戦争体験者の祖父が孫に、戦争の恐ろしさを理解させようとした出来事であることをご理解いただければ幸いです。
私は空き地でゴミを集めて焚火をし、拾ったラムネの瓶を火の中に入れてみました。
しかし何度、火の中に入れても瓶は焦げるだけで形は少しも変わりませんでした。
不思議に思い、母方の祖父に相談しました。
すると祖父は「そんな弱い火ではあかん。原子爆弾の炎や熱は一瞬で周囲を焼き尽くすほど強いんや」と言いました。
そして一緒に廃材を集め、井桁に組み上げた中へ瓶を入れ、さらに当時よく使われていた家庭用簡易懐炉に使うベンジンを大量に注ぎました。
ほどなくして燃え上がり、その火力と炎は、子供だった私が想像できる範囲をはるかに超えていて、本能が危険を告げて膝が震え、言葉も出ないほどの衝撃を受けるものでした。
そして火が落ち着いた後、瓶を取り出すと、広島で見たあの「原子爆弾の熱と炎で歪んだ瓶」と同じ姿になっていたのです。
そのとき私はようやく理解しました。あの瓶は信じがたいほどの炎と熱量がもたらした破壊と死の象徴だったのだと・・・・。
そして実際に、広島や長崎という街に暮らしていた人々は、あの業火で焼かれたのだと気づいた時、小学生の私は、戦争というものが怖くて悲しくて堪らなくなりました。
二度と戦争を起こさないために、核を持たないのか持つのか?
2025年現在、世界では約1万2000発以上の核弾頭が存在し、そのうち約9600発が軍事利用可能な状態にあるそうです。しかも一部は即時発射可能な警戒態勢に置かれているという現実があります。
これまで世界の警察官であったアメリカがその役割から降りようとしています。
ルールに基づく国際秩序から、パワー(経済力・軍事力)に基づく国際秩序へと傾きつつあるという見方が広がっています。
今回のトランプ関税のように、経済と安全保障が一体化した世界で、私達は今後どうやって自分達の国を守って行くのか?軍事的自立はどうするのか?核政策はどうするのか?
願う平和ではなく、皆で考えて選び取る平和を、今を生きる私たちの責任として作りたいですね。