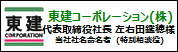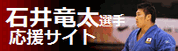先般、土曜日の夕方から関連先も交えた会議が当社であった。
土曜日は女性社員が出勤していないので、手の空いた私が会議用のお茶菓子を買いに出た。
会社の近くにあるいつもの和菓子屋に行くと、入口のガラスに「月見だんご予約受付中」と張り紙がしてあった。
それを見てまた今年も、生涯忘れることが出来ない月見の日の出来事を思い出した。
私が物心付いた頃には、すでに母は闘病中だったこともあり、そして母自身が若かったこともあり、我が家では季節の伝統行事はほとんど行われなかった。
しかし何故だろうか、今となっては聞くすべもないが、お月見だけは母が一時帰宅している限りは年ごとに行ってくれており、幼稚園児の時からの月見の記憶がある。
当時、父は12時間隔週昼夜2交代制の工場勤務だったので、昼の勤務の時であっても仕事が終わる時間が遅く、私の起きている時間にはほとんど帰宅出来なかった為、記憶の中の月見は大部分が母と二人きりのものである。
母は一緒に月を眺めながら色々な話をしてくれた。
月の表面の模様がウサギの餅つきに見える話から、自分の生い立ちや子供時代の話まで、私の年齢に合わせた話をその都度聞かせてくれた。
中でも小学3年生の時の母と二人の月見は生涯忘れることが出来ない。
今思えば、絵に描いたような月見の風景だったように思う。
満月の見える窓を開けて、小さなテーブルの上に、近所で採ってきたススキを生けた花瓶と月見だんごを盛った皿が飾られた。
当時は今と違い、泉南は大阪の田舎ということもあり空気も澄んで、街灯や照明類も少なかったので、今よりも月が煌々と神秘的に光っていたように思う。
母は月を見ながら、私を生んで暫くしてから「重い病気になったこと」から語り始めた。
母の入院する病院へ祖母に連れられてお見舞いに行くことが日常的に多かったので、子供ながらに母が簡単ではない病と闘っていることは、漠然と分かっているつもりでいた。
しかし改めて母の口から直接「すごく重い病気に罹っていること」、「物心のつかない内から何度も親戚に預け、私に寂しい思いをさせていること」、「たとえどんなに苦しくてもなるべく自宅に居て私と1秒でも長く一緒に居たいと願っていること」、「これから医学が余程進まない限り、私が大人になる頃まではもう生きていないと思うこと」などを聞かされた。
この世が終わって自分自身も消えてしまうと思えるほどの衝撃を受け、全身が震え出しそうな不安に襲われたこと、哀しみが溢れ出そうになったことを今も鮮明に思い出す。
自身が決壊しそうになり、私は母に
「何も聞きたくない、何も見たくない、何も考えたくない」と言った。
双眸に涙を浮かべ泣くのを堪えている母の顔を見ていると言えなかったが、「母が死んだら一緒に死にたい」と本当は言いたかった記憶まである。
しかし気丈にも母は、泣き出しそうになる私に「男の子は私が死んでも泣いたらアカン」と言い放ち、最後に「ごめんね」と一言ポツリと言って無言になった。
この後、母は年々、腎機能が低下して入退院の頻度を増していき、ここから数年先には人工透析を始めるまでに進行して行った。
そしてこれが最後の自宅での「母と二人の月見」になった。