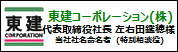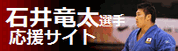2013年
7月
26日
金
仕事は楽しい51% 仕事は苦しい49%

ちなみに上の数字は私の心を数値化したものである。
仕事が楽しいと思える時は、まず思い浮かぶのは「三方良し」が実感出来た瞬間である。
お客様の満足、従業員の幸せや会社の利益、社会への貢献、この三つを実感出来た時はやはり嬉しいし胸を張って「仕事が好きだ!仕事が楽しい!」と言える。
仕事が苦しいと思う時は、経営者にとって当たり前の事だろうが、計画通りに売り上げや利益が上がらない時だろう。
2番目は、やりたい企画が沢山有り過ぎて、時間がいつも足りないことである。
お蔭様で近年は恒常的に忙しいのだが、仕事が暇だった時期も何とかしようと思って動き回っていたし、今後もそうすると思うので、とにかくいつも時間に追われていて苦しい。
3番目が一年中、寝不足であることが苦しい。
寝不足の原因は、柔道で鍛えた肉体に対する過信とオーバーワーク、そして私自身の時間配分の下手さが原因である。
何もかも順調な時だって不安で苦しくなる。
順調であればあるほど、手抜かりがないか?落とし穴はないか?と、暗雲が立ち込めるように不安が追いかけてくる。
その結果、いつも心が晴れることは無い。でもこれも経営者ならたぶんほとんど全員がそうだろう。
そして自分が背負う「責任」を考える苦しくなる。
細かく数え上げたらきりがないが、大きくまとめると、まず製造業であるが故、作った製品に対するPL責任に始まり、出資者や債務・債権者に対する金銭面での企業責任、雇用全般を含む社員や下請けさんに対する生活・仕事の保障、労働環境を含め一人一人の社会的立場と人権に対する配慮、地球環境問題への取り組み、コンプライアンス(順法)の義務等を含む社会的責任、・・・・・果ては地域のコミュニティーや業界団体・同業他社にまで社会的責任と配慮を持って対処していかなければならないのである。
これらのすべての責任を1つでもおざなりにしてしまうと、会社の危機にまで陥るのである。
しかし経営者として生きるからには常々「戒め」と「危機感」を持って歩いていくしか方法はないのである。つまり「苦しさ」を抱えながら生きて行くしかないのである。
それが嫌なら、全てを放り出して辞めてしまうか。
正直な話、私の気持ちは「死ぬまでやるぞ」が51%、「もう辞めて、のんびりするぞ!」が49%というぎりぎりのバランスで成り立っている。
しかしながらこのバランスが逆転する事は、この先も絶対にない。
それは「どんな逆境においても何くそ負けるものか!」「どんな時でも諦めず、気の遠くなるまで繰り返す!」という柔道で培った精神が私にはあるからである。
苦しい事から逃げて楽な道を選んだら、私が私でなくなる。
「もうやめるぞ」という弱気な自分に、「死ぬまでやるぞ」という強い自分が常に勝ち続ける。
この自己闘争の勝利こそ私の「生きる証」と言っても過言ではない。
きっと私は何かと闘っているが好きな人間なのだろう。 笑
2013年
7月
18日
木
祈りが通じた日

高校3年生の夏のインターハイ、決勝戦での不思議な話。
その4ヶ月前の春の全国大会で優勝した私たち柔道部は、春夏連覇の大目標を掲げ皆一丸となっていた。
何度も土俵際に追い込まれながらもギリギリの所で踏みとどまり、決勝戦まで勝ち進んでいた。
皆の興奮や熱気を全身で感じながら、私の心はズシリと負い目を感じていた。
春の大会で切れた靭帯と潰れた半月板が完治せず、それが原因で私の足は思うように動かないでいた。
その為、私は2回戦から準決勝まで3回連続で負け続け、仲間たちに首の皮一枚の苦戦を強いてしまっていた。
いよいよ決勝戦。
決勝戦は5人戦で私が大将だった。
幸か不幸か1勝1敗2引分、しかし内容負けの状態で自分の出番を迎えることになってしまった。
引き分けても負けで、勝たない限り優勝はない。
あの当時の我々には「準優勝」は初戦敗退と同じなのであった。
「全国優勝」のみを手に入れる為に、皆の青春の全てと、練習漬けの難行苦行の日々はあった。
そしてこの試合は私たち3年生にとって最後の試合でもあった。
猛烈に重たいモノが私の肩にかかった訳だが、私の足は怪我で動かず3連敗中。
はっきり言って高校生活最大のピンチ、絶体絶命である。
「えらい事になってしまった・・・」
心臓がドクンドクンと波打ち、拳の中は汗でまみれている。
「死んでもいいから勝ちたい!神様!!」
そんな難局で思い出したのが、天理柔道会の会長をされていた中山正信先生の言葉であった。
「試合でここ一番困ったり苦しんだりした時は、取り敢えず理屈ぬきに心の中で祈ってみろ!」
私は無我夢中に一心に祈った。
ただひたすら一心に念じていたせいか、いまだに夢のようで、祈っていた事以外その間の記憶がない。
私の心の中は不安も恐れも迷いもなくなり、あるのは「祈り」だけであった。
「立花~!」という声援が耳に入り、ハッ!と我に返ると開始線に立っていた。
声の主は応援に来てくれていた左右田社長のものだと判別出来たぐらい頭の隅は落ち着いていた。
試合が始まってみると、どういう訳か足の痛みが消えていた。
準決勝までは満足に動かなかった左足が100%の能力で試合の間だけは動くようになっていた。
そしておかげさまで私は1本勝ちすることが出来て逆転勝ちし、春夏連続全国優勝させて頂く事ができたのである。
試合後に分かったことであるが、柔道部の皆も中山先生の言葉を思い出し、心の中で叫びながら祈ってくれていたそうだ。
のちに見たビデオ映像には、手を合わせながら私を応援してくれている仲間たちの姿が写っていた。
<第28回 全国高等学校総合体育大会 優勝決定の瞬間>

2013年
7月
11日
木
式年遷宮

本年は伊勢神宮の第62回式年遷宮の年である。
20年に1度正殿を建て替え、御神体を新たな社殿に遷す「遷御の儀」が行われる。
ところで私が初めて伊勢神宮に参拝させて頂いたのは、40年前の第60回式年遷宮の年である。小学6年生の修学旅行であった。
厳粛で静謐な空気。青々と茂る見事な木々。凛とした真新しい社殿。そこはまるで俗界から隔絶された世界のようであった。
幼少の頃より祖母に連れられて神社・仏閣の類いはたくさん参拝していたから尚更この場所が何か特別な存在であることが子供ながらに感じられた。
前置きが長くなってしまったが、実は当社は今回の式年遷宮に間接的にだが、少しだけ関わりを持たせて頂いているのである。
というのは遷宮に際して、3年前より始まった社殿建築に使用する材木の切り出し後の保管養生に、当社の毛布をご使用いただいているのである。
当初、現地の伊勢神宮御用達の代理店さまより、「今回は寝具として使用するのでは無いのだが、丈夫で燃えなくて水分を含んでも腐らず、尚且つクッション性のある真っ白い毛布はありませんか?」とご連絡を頂いた。
毛布を寝具に使用しないのなら一体何に使用するのだろうかと、お話を詳しく伺うと上記の内容をお聞かせ頂いたのである。
そこで当社の難燃毛布はカビや雑菌等に因る生化学分解や腐食性に優れていることに加えて、国土交通省や消防庁の公的機関より正式な認可を頂いた難燃性であること。また色展開に白が有ることをご説明差し上げた。
するとすぐさまテスト用のサンプル毛布の送付依頼を受けた。
日本人にとって伊勢神宮は別格の存在である。
その伊勢神宮の遷宮に当社の毛布を使って頂けるのならこれほど光栄なことはない。
グループ内の「紡績、織屋、起毛屋、ミシン屋さん等」に事情説明の連絡を入れると皆さんも喜んで、「こんな仕事をさせて頂けるだけで有難い。無料でもいい!!」と言い出す始末であった。
サンプルを提出後4~5日してオーダーを頂いたが、この時ほど自分の首がキリンのように長く感じたことは無かった。
「無料でいいよ」と言った皆の言葉は本心であったが、しかし無料というのは代理店さまにも失礼にあたるし、生業と為す商いの道にも背くことになり、ましてや神意に背くことになるのではと考えた。
しかし縁あって式年遷宮に係わる仕事をさせて頂け有難く思っている気持ちをどうしても氏神様にお伝えしたかった。
そこで商売とは別の次元で、皆でお伊勢さんに「お供え」させて頂こうと提案しグループ全社から大賛同を頂いた。
一般の参拝の方たちに混じり授与所で名乗らずお供えさせて頂いた。
それですぐ帰るつもりであったが、祈祷を受けに来た者と勘違いされたようで、思いがけずも有難くご祈祷を受けることになった。
御神前に捧げられる高雅な雅楽や舞に見惚れながら、日本人としてまた企業家として、遷宮に係わる仕事を頂けた喜びを噛みしめた。
このような仕事を頂けたのも、創業以来たくさんの方々の支えが有ったからだと感謝し、またこの事は私も含めてグループ内の社員全員の「働きがい」や「励み」にもなると思い、ブログに書かせて頂いた次第なのである。
2013年
7月
04日
木
価格競争には参加しない

昨今、色々な業界において「低価格商品」の拡充が目立つ。
衣料品ではファストファッションが流行しているし、家具は昔に比べるとずっと安い金額で手に入るし、家電製品もどんどん安くなっている。
当社の主要製品は毛布だが、それだって海外から低価格商品が大量に流入して来ている。
「価格競争が大変でしょう?」と聞かれることもあるが、実のところちっとも大変ではない。なぜなら当社は価格競争には参加しないからである。
低価格商品というのは、低価格でも利益が出るように、価格に応じた費用で物作りをしている。
昔、「美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりに写ります」というカメラのCMがあったが、低価格の商品は、材料にしろ技術面にしろ、それなりのレベルの商品なのである。
「安いから」という理由で商品を選ぶ消費者はそれ以上に安い価格が出た場合、すぐさまそちらへと移行する。その消費者を取り戻す為には、更なる値下げが必要である。
そうなると商品の質は言わずもがなである。
だから当社では低価格を売りにした物づくりはしない。値下げ競争にも参加しない。
しかし競争になるのは、他社の商品が当社と同品質で、それが同じ価格帯だった時である。
その場合、品質を落とさずに値下げをするという方法もあるが、製造業者にとって値下げというのは後ろ向きの手段である。
また一度、値下げしてしまうと元の価格に戻すのは至難の技である。もし戻せたとしても、待っているのは「客離れ」のみである。
値下げをせず、シェアを増やすには・・・
1、コマーシャルの重要性
気合や根性で営業をして売れたのは昔の話である。
今は何を置いてもまずメディア戦略である。
少しでも多くの人の目に触れるようにコマーシャルの徹底した拡散が必要である。
それはHP等に始まり、パンフレットや販売に必要なビジネスアイテムの充実、広告宣伝活動の拡大が必要。
2、宣伝活動の継続性
継続は力なりと言われるが、1度や2度のコマーシャルではすぐに忘れられてしまう。
継続することが重要なのである。
余談ではあるが、経営者が営業方針や考えを現場に落とし込む際にも、一度や二度伝えただけで浸透しないことに嘆くことなく、何度も何度も語り掛けなければならない。人間の脳は時間経過した情報は忘却する構造なのだ!と認識し、諦めず繰り返えさなければならない。
3、販売流通経路への気配り
製造業を支えてくださる販売網への細かい気配りを常に心掛け、どんな些細なことでも意見をよく聞きながら日々、修正・改善を行い、少しでも販売店が売り易い環境を提供していくことに最大限の配慮を行うこと。
4、ブランド性の確立
ブランド性とは言わば安心と信頼の浸透である。その為には気の遠くなるほどの時間が必要であるが、1~3を真摯に受け止めて継続することで、結果は歴史が証明してくれることと思う。
しかし今この瞬間にも世界は動いている。
1~4だけを忠実に続けていけば会社は存続出来るという時代では、もうない。
京都の職人が何ヶ月もかけて作った工芸品を、3Dプリンターがいとも簡単に短時間で再現してしまう時代なのだ。
1年先には、日本の物づくりがガラッと変化していることだってありえる時代なのだ。
時代の変化に取り残されないためにも経営者に必要なのは「たえず見直すこと・そして次の一手を打ち続けること」であろう!