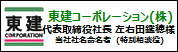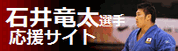2013年
2月
26日
火
社長の役割

社長の役割とは何だろうか?
大企業の社長の役割と、中小企業の社長の役割とは、同じ社長という肩書きであっても大きく違うだろう。
同じ中小企業の社長であっても、成長期の会社と成熟期の会社とでは、社長の役割は違うだろう。
「社長さん自らそんな事までするの!?」
私が周りから、よく言われる言葉である。
それはトイレ掃除に始まり一般業務、営業、機械操作、社長業に渡るまで私は会社のすべての内容を把握している。だから、いついかなる時に欠員があっても即戦力として全ての業務に携わることが出来る。
また、常に先頭に立って走るように心掛けている。
このような姿勢を学んだのは、私の師匠である左右田鑑穂社長からである。
今から35年ほど前、東建コーポレーション(株)が東名商事(株)という中小企業の時代に、私はすぐそばで師事させて頂いた。
その際に、どんな仕事にも自ら先頭に立ち、誰よりも働く左右田社長の姿を日々目の当たりにし、成長期の中小企業の社長の姿というものを学んだ。
だから私の信念は、「社長自ら先頭に立って仕事をさせて頂く!」である。
以前、とある来客が当社を訪れた際に「ここの社長はいつ来てもいない!」と恨み言を残して帰ったことがあった。私はそれを聞いてかなり腹が立って、来客に電話を入れた。
「中小企業というものは、社長自ら先頭に立ちトップセールスマンとして営業に歩くものであって、会社に居ないことの方が当たり前であり、いつも社長が会社の椅子に座っているのは、今の厳しい時代にこの先、倒産する会社だ!」と。
しかし年月が流れ、会社の規模や、私自身の年齢や体力も変化して来た。
今はまだ自分が先頭に立ち機関車のように会社を引っ張っているが、私もいずれ歳には勝てなくなって、先頭に立てなくなる時が来るだろう。
師匠からも、「機関車型の組織から、新幹線型の組織へと移行していけ」と助言を頂いている。
新幹線型というのは、複数の車両に動力を備えた「動力分散方式」のことだ。
動力を備えた車両を増やすには、人材育成そして組織作りに一層取り組んで行かなければならない。
それが今の私の重要な仕事の一つだろう。
会社の成長によって社長の役割は変わって行く。
会社の成熟が進めば、社員一人一人の抱える責任が重くなるだろうし、判断を任される機会が増えて悩んだりするだろう。
けれども、そのようにして社員も会社も成長して行くのだと思う。
先にも書いたように私の信念は、「社長自ら先頭に立って仕事をさせて頂く!」だ。
いつまでもそうしていたいと思う願望と、いつもでもこのままじゃいれない現実との狭間に、今私は居る。
2013年
2月
16日
土
二人のがばいばあちゃん

「驚愕するほどの凄まじい生きざまのおばあちゃんの物語」
・・という広告に魅かれて、何年か前に漫才師・島田洋七氏の「がばいばあちゃん」を読んだ。
驚愕する気持ちは起こらなかったが、懐かしい想いが湧いた。
私の祖母も、近所の悪ガキをほうきを持って追い掛け回したり、男達に混じって働くような、がばい(すごい)ばあちゃんだった。
私が幼い時に預けられていた母方の祖母は、とにかくお金と仕事には厳しい人だった。
その時代の皆がそうであったように、兄弟の多い貧しい家庭で祖母は育ったそうだ。
人一倍の働き者で、私を背負って家業の大工仕事を手伝ったり野良仕事をしたりするものだから、お蔭で祖母が背中を曲げる度に私は胸が圧迫され苦しかった記憶がぼんやりとある。
「男から仕事を取ったら何も残らへん」「男の金の無いのは首が無いのと同じやで」などと幾度も聞かされた。
そんなわけで、男にとって「仕事」と「金」は必要不可欠なモノなのだと、子供ながらに理解した。
祖母のその言葉は、今も私の衷心になかなかの存在感を放ちながら常駐している。
私を躾ける際にも「金」の話が出て来た。
「子供の時にゴミ拾ろたら、拾た分だけ大人になったらお金ひろうで」「朝早く起きたら道にお金が落ちてるで」など。
今考えると笑ってしまうが、その当時は本当に一人で早起きをして、誰にも取られまいと目を皿のようにしてゴミを探し歩いていたので、私の本来の目的を知らない第三者が見れば良い子だったかもしれない。
一方、父方の祖母である丸竹COの前身立花屋を創業したきくえばあちゃんは、優しく大らかで信仰深い人であった。
年長の子供に、「お墓の下には人骨があるんや」と聞かされて怖がる私に、「恐ないから墓参りに付いておいで、ご先祖様の骨があるからアンタが生まれて来たんやで」と話してくれたり、「神様も仏さまもほんまに居てるで、見てるで」と教えてくれたりした。
こんな事があった。
骨董屋の店先に飾ってあった大きな壷を、私がやんちゃを働いて割ってしまった。
驚きと後悔と罪悪感で泣き出した私を祖母は「だいじょうぶやで。この世であったことはこの世で納まる」と慰め、何の愚痴も言わずに弁償金を支払ってくれた。
「この世であったことはこの世で納まる」
これは祖母の口癖であった。
祖母に相談に訪れた大人たちも「この世であったことはこの世で納まる」と言われると、皆どことなく安堵の表情を浮かべて帰って行った。
私自身もいつもこの言葉を思い出し、心のより所にしている。
こうして思い出せば二人の祖母から、お金のこと、仕事のこと、心がけや信仰心、感謝の気持ちなど沢山のことを教えてもらった。
自分が教えてもらったことを、私はちゃんと次の世代に継げられているだろうか?
心の中で問いかけてみると、「まだまだアカンわ」「そやな。アカンな」と笑ってるばあちゃん達の姿が見えた気がした。
2013年
2月
03日
日
天下人に学ぶ

いきなりだが徳川家康が天下を取れたのは、家康が信長や秀吉よりも長生きであったからだ、と私は思っている。
もちろんそれ以外の要因があったのは言うまでもないが。
日本人の平均寿命が35歳の時に家康は75才まで生きたそうだから、抜群の長寿だ。
家康は運に恵まれていたから、長寿を手に入れることが出来たのか?と言えばそうではない。
実は家康は非常に健康に気を使っていたようで、医薬の勉強を熱心にしたり、当時最先端の薬をいろいろと取り寄せたり、足腰の鍛錬はもちろんのこと、驚いたことにダイエットまでしていたそうだ。
そのように健康の追求をした結果が、人並みはずれた長寿だったのだろう。
家康は健康に長生きしたからこそ、沢山の時間を手に入れ、多くのことを実現して来た。
時間というものは、皆に平等に与えられているようでいて、実はそうではないかもしれない。
人より長く健康に生きれば、そのぶん多くの時間が手に入る。
多くの時間が手に入れば、その分やりたいことが出来る。
私は長年、仕事の忙しさを言い訳に必要最低限の健康管理しかして来なかった。
ずっと勧められていた人間ドックも「時間がない!」と断っていた。
自分の体を懸念しつつも、健康管理の優先順位をいつも後回しにしていた。
けれども最近思うのだ。
健康管理こそ最重要の仕事なのではないかと。
長期的な観点で考えれば、社長である私が健康な身体・健全な精神で居ることが、今目の前にある仕事を片付けるよりも、会社の為、社員の為、延いてはお得意先の為になるのではないかと。
そう思い、仕事の手を止めて時間を無理やりにでも作って、一昨年より4ヶ月に1度の徹底的なドック検査を受けている。
先生によれば、真面目に検査に通って健康管理をすれば、あと30年は寿命を保証してくれるらしい。
まだまだやれるぞ!だから皆、安心して俺について来てくれよ!と胸を張ると
「家康に見習ってダイエットもして下さいよ」と社員から返ってきた。